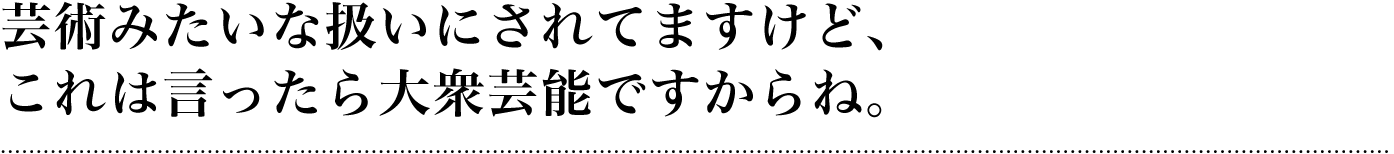いつしか接点を持つことが少なくなった日本の伝統芸能。何百年も続いている文化と、再び接続することで見えてくる、本当の “日本らしさ” があるのではないか。文楽の技芸員(三味線)の鶴澤清志郎さんに文楽の魅力についてうかがいました。
後藤「ここ何年かの話なのですが、音楽をやっていて、自分たちのナショナル・アイデンティティっていうんですか、例えば日本の伝統音楽なんかと上手く接続出来てないんだなってことをよく考えるようになったんです」
清志郎「そうなんですか?」
後藤「僕らは小学校の時からドレミファソラシドで音楽学びますよね?」
清志郎「そうですよね、はい。確かに日本の音階とは違います」
後藤「例えば文楽を観に来たときとか、能でもいいですし歌舞伎でもいいかもしれないですけど、その鳴っている音に対して “わー、懐かしい” みたいな感覚っていうのがやっぱりないんですよね。正月とか、そういう時に飲食店でかかっているお琴とか、それくらいしか馴染みがないっていうのが不思議で」

清志郎「三味線音楽にも色々あって、僕らのやっている義太夫節っていうジャンルは滅多に流れないですね。お正月でも義太夫節が流れることはほとんどないでしょう。そういう時に流れてくる音楽というのは、もうちょっと華やかな三味線が多いですからね」
後藤「あとは、たまにNHKやNHK教育で放送されているときがあります。そのくらいのものですよね。自分たちが現代を生きているなかで、こうやって文楽のように伝統として続いてきてるものと、僕らみたいな一般庶民との距離が開いているようにも感じて、 “怖いな”という気持ちがいつしか湧いてきて…。それで今日は、文楽に携わっている方に話を聞きに行ってみようということでお邪魔しました」
清志郎「ありがとうございます。そうですよね、馴染みが薄いっていうのもありますし。ちょっと遠いものとか、芸術みたいな扱いにされてますけど、これは言ったら大衆芸能ですからね」
後藤「元々はそういうことですもんね。今回観させていただいた『曾根崎心中(※1)』も、きっと江戸時代の町人たちが、わいわい言って観ていたものですよね」
清志郎「そうです、内容もそんなになんていうか気高い崇高な内容ではないですし。前回も『曾根崎心中』をご覧になったんですか?」
後藤「いや。お正月の公演でした。初めての観劇だったので、いろいろとカルチャーショックを受けました」
清志郎「そうですか。退屈しなかったですか?」
後藤「いや、退屈ではなかったですね。ただ、人形の動き、大夫さんの声、三味線や琴、情報量が多くて、どこに集中していいのか分からなかったというのはありました。(笑)」

清志郎「そうですよね。こう場所が散ってますもんね。右手の張り出した舞台(床)では大夫さんが語ってて、人形さんが正面にいますから」
後藤「初っ端から、玄人と同じようなやり方で全体を観たら絶対ついていけないと思ったので、目を皿にするというか、とにかく大夫でも三味線でも人形でも、どれかひとつでも一番良いなと思うところを感じて帰ろうという気持ちで観ました。今日もやっぱりそうやって観ていて、『曾根崎心中』の最初に、徳兵衛(※2)がシャっと出てきた時の、なんというんですかね、粋な感じというか、そういう雰囲気というのを感じる楽しみもあるんだなって」
清志郎「そうですね。抜けたあの、ふっと姿勢の良い感じがきれいですよね。背筋がぴんと伸びていて。幕から出てきた瞬間がすごく大事だというのは、先輩、師匠方もよく言われますし、本当に不思議です。あれは人形というものがあるからそう見えているわけじゃないんですよね。やっぱり人形遣いさんの技術が、そういうところにもちゃんとあって、おそらく真っ白のマネキンみたいな人形でやっても、これは武将が出てきたとか、町人が出てきたというのは、お客さんに伝わるんですよ。そういう細かな技術を使ってやっているんです」

後藤「僕はミュージシャンなので、どうしても楽器が気になるんですよね。それで、大夫さんの声もそれぞれ違うじゃないですか? 観ているうちに、さっきの人と今の人どう違うのかというところも気になってきて」
清志郎「不思議ですよね? 僕も文楽って不思議だなって思うんですけど、(大夫と三味線弾きが演奏していたところの床が)クルっと回ったらさっきまでと違う大夫さんに替わって、同じ役(人形)なのに違う人の声で、続きの場面が語られるわけだから、お客さんもよくついてきてくださるなと思います。一人一役じゃないですからね(文楽は場面ごとに大夫と三味線が入れ替わり、その際、座っている床を回転させて、退場と登場を同時に行う)」

後藤「今日観ていて印象的だったのは、2つ目の段のときに、——すみません、ちゃんと覚えてなくて。『天満屋の段(※3)』ですね。『天満屋の段』の時の三味線って、どういう理屈で覚えてらっしゃるのかが全く分からなくて、決まった拍もないですし」
清志郎「そうなんですよね。もう走ったり戻ったりうねるようなリズムの中で」
後藤「それでなんかこう合いの手をさっと入れているような」
清志郎「そうですね。本当に絶妙なんで、僕らでも完全に理解できないこともあるんですけど。でもそれは声楽であるということが大きいと思いますね。大夫さんとの呼吸を弾いてるっていうところがあるので。大夫のリズムを引っ張りながら助けていくっていうのもあって、自分で決められるものだけではないんです。自分だけなら、ずっと演奏として先に先に行けるんだと思うんですけど、助けたり足引っ張ったり、うねりながら弾かなきゃいけないので」
後藤「グワァっと緩んで、三味線と声がかなり離れてるところもありました」
清志郎「流石ですね。そういうところは、合わないように合わないようにやるものなんです。出来るだけ合わないように、バラバラになるように、かと言って乱れないようにっていう」
後藤「でも、ふっと、キュって一緒に揃ってやるところもありますよね? 一瞬、意識的に乗っかったんじゃないのかなって思ったりもするんですけど、よくよく聞いてると、またハーって離れていく」

清志郎「大夫と三味線弾きは人形さんを見てないんです。人形の方を見ながら演奏するのではない。でもやっぱり人形が苦しむ場面だったら、のたうち回る振りのできる速度っていうのがあるでしょうし、隠れて逃げて行く場合だったら、やっぱり恐る恐る弾くっていう、考えたらなんとなく想像つくのもあります。一方で、馴染むようにやると、かえってそのリズムが乱れたりして…。そういうところだと思います」
後藤「おもしろかったです。僕らのやってる音楽は、基本的に “いかに合わせるか” っていう文化が元なので。ビートだったり音階だったり」
清志郎「リズムがそうですよね。僕らも実際に “音楽” をやるならそれが絶対条件だと思うんですけど、これはもう “語り” なので。落語とかと一緒の、三味線の入った語り芸です。音楽であって音楽でないので」
後藤「なるほど。そのあたり、興味深いですよね。日本の芸能って語り芸の要素が強いですよね、やっぱり」
清志郎「なんでそうなるのか、僕もあまり難しいことが分からないですけど。文章の入った音楽でもそうなんですけど、インストルメンタルっていうんですか、音楽だけのものよりも、ちゃんと言葉がついたもののほうが人気がありそうですし、ほんまに」
後藤「歌詞を気にしますからね。日本人は」
清志郎「言葉というものをすごく大事にする民族だなと思います。だからこういう語り物というものが愛されるというか、昔から誰かに話してもらうのが好きな民族なんでしょうね。まだ字が読めない人ばっかりの時代にできたものでしょうから」


鶴澤清志郎(つるざわ・せいしろう)
1974年長野県生まれ。1992年に国立文楽劇場第15期研修生となり、1994年に鶴澤清治に入門。清志郎と名乗る。同年6月、国立文楽劇場で初舞台。
(※1)曾根崎心中
近松門左衛門作の世話物浄瑠璃。初演は江戸時代中期。大坂の醤油屋の手代徳兵衛と遊女のお初が天神の森(大阪市北区曽根崎)で心中した事件を、わずか一ヶ月後に脚色し上演、話題になった。
(※2)徳兵衛
『曾根崎心中』の登場人物。大坂の醤油屋の手代。手代とは、番頭と丁稚の間にあたる使用人。叔父にあたる醤油屋の主人に持ちかけられた縁談を断り、遊女のお初との結婚を決意するが、主人から継母に渡された結納金を友人である九平次にだまし取られ、お初との情死を決意する。
(※3)天満屋の段
『曾根崎心中』の第二幕。 最後の別れを告げに来た徳平衛を、お初は天満屋(女郎屋)の縁側の下に招き入れ、ふたりは心中を決意する。