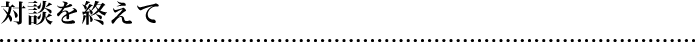園「今回の映画は制作費に本当に苦労しました。原発問題はタブーですからって断られ続けました。日本人に見せようと思って作ったのに、結局は海外からお金をもらって作ったんです。情けないですよね。アメリカの映画界はなんでもビジネスにするアクドさもあるけど、たぶんこの映画にはいろんな意味で興味を持つだろうなと交渉しました。それはそれで、僕の言いたいことを言わせてくれるんならアリだとも思ったし」
後藤「やっぱりテーマ的にお金って全然集まらないんですか?」
園「全然、ダメですね。物言えば唇なんたらで、映画会社としたらそんなリスクを冒したくない。それこそ、忌野清志郎がレコード会社と訣別したときと似たようなことがあるのかな。でも、日本の映画界はそれとは違うかもしれないです。こないだChim↑Pom(※5)という芸術集団と話したんだけど、やっぱりアートはアートなりの困難さがあるし、音楽家も音楽家の困難さがある」
後藤「音楽の歌詞って、昔よりは、厳しくなくなってますけどね。僕も総理大臣の悪口とか唄の中でありますけど、なんにもリアクションないというか。ただ、音楽番組なんかに出るとき『後藤さん、NO NUKES Tシャツとか着ないでください』って言われたことはありますけど。それがなぜかは全然よくわからない」
園「それって怖いね。単純に自主規制ですよね。向こうを、というか相手の背後を立てるためだと思うんだけど。その背後の人だって、誰も気にしてなかったりするからね」
後藤「そう思うんですけど。誰も気にしないのに、なんで気にするんだろう?って」
園「そんな不思議は、この世界には一杯あると思うんですけど……特に映画界は、そうしたものと直結してるんですよ。テレビ局まで来ると、最後はもう、お偉い方がカーテンの向こうに座ってるからね。きっとそういう方のお伺いを立てるんでしょ」
――アメリカだと、なんで大丈夫なんでしょうかね?
園「それはやっぱり、それぞれの党がちゃんと党として成立してて、言いたい放題やりあってるからでしょう。向こうの俳優って、みんな自分の支持する党も言っちゃえるし、闘ってるからね」
後藤「ミュージシャンも言ってますね」

園「イーストウッドは共和党、クルーニーは民主党、とか、ハリウッドなんかそれでバッシリ分かれてる。今回の大統領選も俳優同士で応援合戦してて、言論の自由があるにはある。日本だとそんなこと言ったらメチャクチャになっちゃうし、もしかしたら謝罪もしなくちゃいけない。昔の俳優は、(菅原)文太とか『ウチは共産党じゃい』なんて言えた時代があったけど、今は自主規制の嵐のせいで、みんな押し黙っていて。言論の自由というものが、もうなんだかわからなくなってきてます」
後藤「そうなんですよ」
園「アメリカはまだなんとなく、そのあたりの自由があると思うんですよね。ポール・トーマス・アンダーソンが『ザ・マスター』(2011年)という映画を撮って、アメリカの超巨大な『サイエントロジー』という新興宗教の教祖を描いたりして。日本であれと同じものを撮ったら、間違いなく命を狙われるだろうし。そういう意味では、守られてるっていいなと思いましたね」
――ちなみに園監督にとっての「暴力」って、どんなものですか?

希望の国 : 全国公開中
園「やっぱり『希望の国』でモデルになった鈴木さんのお宅のように『ここから先には入っちゃダメ』っていうのが、今は一番の暴力だと思いますね。映画の中のお父さんとお母さんも、その場に居続けていいと思うんですよ。その場所から出なきゃいけない、というのが非情な暴力だと思う。結局、死ななくてもよかった人たちが死んだりするじゃない。個人の暴力ってギリギリ自由でいいと思うんです。でも国家が及ぼす暴力というのは非常に冷徹で、感情がないですよ」
後藤「きっとそうですね」
園「肩が当たった当たらない、そんなくだらないことで暴力があったとしても、まだ肩が当たったって理由があるわけで。肩も当たってやしない、なんでもない他人が突然やってきて、線を引いて、はい、出て行けって。それこそスゴい暴力だと今は思いますね」
後藤「ええ」
園「あと、こういう映画を撮って初めてわかったのは、自分は今まで覚悟のいる映画を撮ったことなかったけど、覚悟がいる、あるいは決意をしなければいけない表現ってすごいんだなと。この映画を撮ることで、初めてその醍醐味を味わえました。覚悟するというのは、ある種、表現としてもダイナミックになるんじゃないかと思うんです、最近は。アメリカ映画なんかは、そういうことを必ずやってる。現在進行形の戦争を批判する『ハート・ロッカー』(監督:キャサリン・ビグロー、2008年)みたいな映画が堂々と世界中に公開されて、アカデミー賞まで獲っちゃうのは、いい意味で商魂があるし。ビジネスとして機能させて、売りつけて、なおかつ批判までしてしまうという」
後藤「すごいですよね。マドンナが出たスーパーボールのハーフタイムショーなんかも驚いたな。アメリカの国民的なスポーツのショーの最後に『Peace』って、アンタらが言うのかって」
園「僕の映画なんて小規模な公開ですが東宝でやっても良かったんじゃないかって(笑)。それくらい、開けっぴろげなのが海外ですよ。そう思うとね、そんなにビクビクしなくてもいいのかなぁ、と感じますね」
後藤「今日は緊張しました……」
園「僕もイヤな汗をかきましたよ(笑)」
後藤「俺、自分が園監督の映画の役者だったら怖いなと思いましたね」
園「演技指導のこと? あれはね、役者が時々すごく良くなるのがわかっているとき、優しく演出すると力がそのまま眠っちゃうので。ちょっとこう、ガツンとやることで全然良くなるのは間違いないから、それでやってるんですけどね。役者には嫌われるかもしれないけど、絶対にそれで良くなるんです。だから、でんでん(※6)さんとかには全然何もやってないですよ」
後藤「あの『冷たい熱帯魚』(監督:園子温、2010年)(※7)のでんでんさん、メチャクチャ怖かったです……」
園「早口で喋ってください、とだけを言って。詐欺師はみんな早口なんで」
後藤「あ、そうだ。『希望の国』を観て、1個だけお聞きしたかったんです。最後のシーンに花が出てきますよね。植えられていたのはサクラソウとアネモネに見えたんですけど、選んだのには意味があるんですか?」
園「うーん、意味ありげですけどね。なぜです?」
後藤「気になったもので。俺、花言葉とか調べるの好きで、アネモネには、愛とか希望って意味があるから」

園「僕も調べました、って言いたいところですが(笑)。映画というのは、監督が全部のディテールを整理できるシンプルな表現じゃなくて、いろんな要素が入ってくる。たぶん、映画にはその偶然を引き寄せる力があるんですよ。『希望の国』では、鈴木さんの隣りの家のモデルとなった犬の名前と、実際に撮影でお借りした家の犬の名前が同じだったとか。『冷たい熱帯魚』のときは、なんとなく熱帯魚店の主は真っ赤なフェラーリに乗っているに違いないと思ったら、行く先々で真っ赤なフェラーリに出会ったりね(笑)」
後藤「はははは(笑)。僕らのアルバム(『ランドマーク』)の最後の曲が『アネモネの咲く春に』という歌なんです。赤いアネモネの花言葉は『愛すること』でサクラソウは『希望』なんですよ。震災の前ですけど、サクラソウも歌(『桜草』)にしたことがあります」
園「そうなんだ。愛と希望を呼び込んだのか。しかし待てよ、助監督が考えて気を利かせたのかもしれないな。彼もそれなりに表現者なので。よく映画は監督だけで作ってるって多くの人が思ってらっしゃるけど、実際はみんなで作っていますからね、映画は」


園子温(その・しおん)
愛知生まれ。映画監督。87年『男の花道』でぴあフィルムフェスティバル(PFF)グランプリ受賞。PFFスカラシップ作品『自転車吐息』はベルリン国際映画祭正式招待。以後、世界の映画祭で高い評価を得る。代表作に『愛のむきだし』(09年)、『冷たい熱帯魚』(11年)など。『恋の罪』(11年)はカンヌ国際映画祭監督週間正式出品。2012年10月『希望の国』公開。12年は「非道に生きる」(朝日出版社)、「希望の国」(リトルモア)などを執筆。最新作『地獄でなぜ悪い』が13年公開。
■注釈
(※5)Chim↑Pom
2005年に東京で結成された6人組のアーティスト集団。東京を拠点にしながら、様々な国での展示会やプロジェクトをグローバルに展開。
(※6)でんでん
1981年、森田芳光監督の映画『の・ようなもの』で、映画デビュー。以降多数の映画やテレビドラマに脇役として出演。2011年、園子温監督の映画『冷たい熱帯魚』で、表では笑顔を見せながら裏では連続殺人鬼という二面性を持った熱帯魚店経営者を演じ、芸歴31年にして初の受賞となった第36回報知映画賞を皮切りに、第35回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞など国内の助演男優賞を次々と受賞し高い評価を得た。
(※7)『冷たい熱帯魚』(2010年)
実在するいくつかの猟奇殺人事件にヒントを得て人間の狂気と極限の愛を、園子温監督が描いたサスペンス。家庭不和の中、熱帯魚店を営む主人公が、ある日出会った同業者の手伝いをするうちに、想像を絶する猟奇殺人事件に巻き込まれていく。主演は、『掌の小説』など数々の邦画に出演しているベテランの吹越満。共演者も『嫌われ松子の一生』の黒沢あすかや『月と嘘と殺人』のでんでんら実力派ぞろい。