
帰村の合言葉は〝かえるかわうち〟。カエルをあしらった旗が役場に掲げられている。遠藤村長は言う。
「壁をよじ登ってるみたいで力強い。合言葉にも、何か説得力あるでしょ」
—避難されてほどなくして、郡山市のビッグパレットに仮庁舎を設置しつつ、役場の機能を移されていますね。
遠藤「実は避難してすぐ、川内村の状況がどうなってるのかっていうのは、情報が入ってきていたんです。村には広域消防の方がずっと残っていたので、密にやりとりをしていました。それに当時の川内村は緊急時避難準備区域に指定されていたので、生活はできないけれど出入りは許されていたんですね。なので、役場の職員も様子を見に戻ったりしてました。それでね、4月から5月の間に、村の空間放射線量もわかりました。実際のところ、僕らが避難した郡山市や同じ30km圏内の地域よりも、村内の線量は低かったんです。それを聞いた時に、ひょっとしたら5年もしなくても戻れるんじないかって、そういう思いが芽生えはじめて……」
—5月に避難所の村民に対して行なわれた聞き取り調査でも、「原子力災害が解決した場合、帰郷したい」
という声が8割を占めていたそうですが……。遠藤「そうなんです。それを受けて、ビッグパレットの脇にできた仮設住宅に村民が移り始めた頃から、“村へ戻るためにどうすればいいのか、何が必要なのか?”ということを具体的に考えようって、職員たちに指示を出しました」
—それもかなり早い段階での判断ですね。
遠藤「かもしれないねぇ。国から指示されるよりも前に、僕らは「復興ビジョン」というものを描きはじめました。中身は除染の進め方、雇用の創出、万一のための避難拠点、村を支えていた農業、林業、畜産を再開するためにはどうしたらいいのかというようなことですね。仮庁舎の中に『復興課』っていう部署を作ってね、ふたりの職員を中心にいろいろと具体案を練っていきました。結果的に復興ビジョンが完成したのは、8月末でしたね。9月末には緊急時避難準備区域の指定が解除されたこともあって、それじゃあ〝2012年の3月末までには除染を完了して村に戻れる環境を作ろう、同時に役場機能も再開しよう〟っていう目標を立てました。そこへ向けて、10月から積極的に仮設住宅の村民たちと懇談会の場を持つようになったわけです」
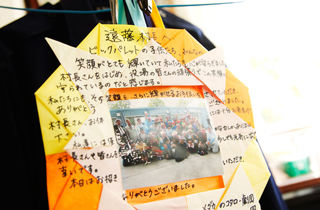
—すごくとんとん拍子に帰村へ向けた動きがが進んでいるように思えます。
遠藤「でもねぇ…………懇談会を重ねれば重ねるほど、みんなで一緒に戻る、あるいは戻るということ自体がどれだけ大変かということを思い知らされましたね。本当は最初12月には帰村宣言をしようかなって思ってたんです。でも、できなかった。やっぱり住民たちのの思いもそれぞれに違うわけで、それをひとつひとつクリアしていくためには相当なエネルギーが必要だって、ひしひしと感じましたね」
—住民の皆さんからは具体的にどんな声が上がったんですか?
遠藤「戻ったとしても働く場所はあるのかっていう意見も多かったけど、やはり一番は線量被爆の健康への影響を心配する声ですよ。特に子供をもつ母親たちの不安は大きかったですね。除染が完全に終わってないのに帰れるわけがないじゃないかって……。線量についてはね、空間線量で考えると1マイクロシーベルト以下の場所が村の大半だったんですよ。僕はね、そういう状況ならば健康への被害はないと考えていいんじゃないかという立場でした。もちろん、根拠なくそう思ったんじゃなくて、僕自身もいろんな文献を読んだり、11月には専門家と一緒にチェルノブイリの視察(※2)もしていました。それでね、チェルノブイリ原発に近いプリピャチという村で、人が住めなくなった街並みがその後どうなっていくのかっていうことを、目の当たりにしたんです。住人がいた時のまま打ち棄てられた家だったり、草木なんかはもう伸び放題でね。事故から25年経った誰もいない村はもう、完全に廃墟っていうんでしょうか…………直視できないくらい、強烈な光景でした。放射線の健康への影響っていうのは専門家でも意見のわかれるところで、もちろん不安を100パーセント払拭することはできません。でもね、どこかで折り合いみたいなものをつける必要があったんですよ」
—折り合い、ですか。
遠藤「実はもうその当時、250人くらいは村に戻ってたんですよ。先に戻った住人たちには、役場機能を早く戻して行政サービスを再開してほしいという願いがあった。同時に、慣れない土地で避難生活を続けることがどれだけストレスを与えているかっていう心配もありました。そうなってくると、このまま避難を続けることと、線量が比較的低い村に戻って元の生活をすること、どちらが住民たちにとってストレスが少ないのか、逆にリスクが高いのか、そういう現実的な判断をしていかなきゃいけない……そんな時期にきていたんですよ。年末から年明けにかけて、じっくり懇談会をやって住民たちと話をする中で、判断を固めていきましたね」
—遠藤村長が福島県庁で帰村宣言を読み上げたのは、2012年1月31日のことでした。
遠藤「本当は最初、“全員で一緒に戻りましょう”って宣言しようと思ってたんです。でもね、戻りたいと強く思ってる人の願いは叶えてあげたいし、戻るのが不安なのも痛いほどわかる。両方の気持ちがそのまま表れて、結果的にああいう“戻りたい人から戻ろう”っていう言い方になりました」
—でも、それがすごく懐が深いというか。避難した人も切り捨てずに、ゆっくり戻ればいいよという姿勢がとても印象的でした。公の機関のイメージというと、もう少しゴリッと線引きをしてしまうイメージがありますから。道路一本で立ち入りの可否を分けてしまうやり方だとか、例えば「20km圏っていうけど、その線引きってなんなんだろう?」というようなことを思っている方もたくさんいらっしゃったと思うんですね。乱暴に線を引きたがる人が多いなかで、ひとつの自治体の長が、「戻りたい人からゆっくり戻ろう」と言えるのはすごいことだなと思いました。
遠藤「いえいえ。僕に言わせると、いい加減な帰村宣言なんですけどね」

(※2)チェルノブイリの視察
福島県や南相馬市の担当者、福島大学の研究者、川内村・遠藤村長など約30人で組織された調査団は、2012年10月31日~11月7日の日程で、1986年のチェルノブイリ原発事故の原子力災害に遭ったウクライナとベラルーシ共和国を視察。汚染地域の現状や被災住民の健康状態、復興へのプロセスを調査する目的で、各地の研究施設などを訪れた
