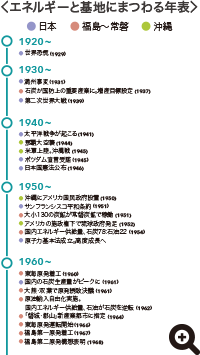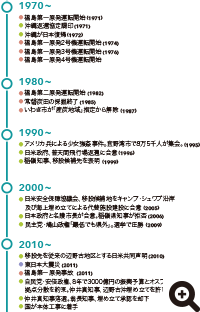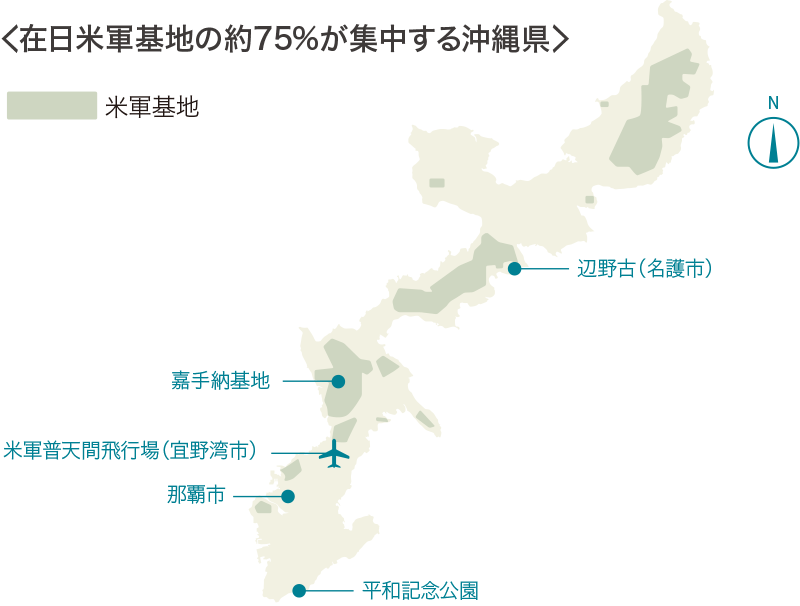
後藤「沖縄では『琉球新報』の記者方が〝外部の人だからこそわかる視点がある〟と言っていましたけど、いざ現地に来てみると、ひと言ふた言でまとめられることって、まったくないですよね。多くの人がTwitterやFacebookでうまいことを書こうとしているけれど、それとは真逆のことをやっていく必要があると思っていて。単純なひと言にまとめて行くことで、問題が体系化されることもあるかもしれないけれど、反面では、多様性を削ぎ落とすことにもなると思う。書くってことは、本当はそれとは真逆で、多様性について書いていかないといけないんじゃないかって」
古川「読むっていう方から考えると、読書をするってことは、世界をクリアにするんじゃなくて、世界ってもともと混沌なんだっていうことを体感させるというかね。嘉手納に行って、戦闘機が飛んでいくのを見て思ったのは、沖縄に来る前は、基地のエリアがあって、〝こっちはアメリカ、こっちは日本〟みたいになってると思ってたんだけど、戦闘機が飛ぶと音は越えてくるから、実際には国境線はない。全部ゴチャゴチャって攪拌される。その攪拌のリアルさをすごく感じた」
後藤「自分たちが認識していたボーダーラインが、いかにフィクション的なもの、便宜的に作られたものなのかっていうことがわかりますよね」
古川「普天間の問題も、危険な住宅密集地にあるっていうことよりも、基地のエリアを越えて、毎日音を浴びせられてることが問題なんだろうなって。どこにあるかってことよりも、その外側まで侵蝕してることが問題なんだっていう、それは現場に来ないとわからない。辺野古が埋め立てられるのが嫌な一番の理由も、あそこが攪拌されて、海が濁るからでしょ? それはすごく本能的な、生き物としての反発のような気がした」

沖縄市、嘉手納町、北谷町にまたがるアメリカ空軍嘉手納飛行場。 早朝、夜間を含めて戦闘機の離着陸は約7万回とされる。
後藤「長いスパンで考えたら、取り返しのつかないことをすごく短い一時期の、インスタントな利益のためにやるんだなって思いますよね。でも、便利に暮らすために、都市化するために、人間として〝ん?〟って思うような、昔だったら〝祟られるんじゃないか?〟と畏怖してきたようなことも、全部どこかに押し付けてきたわけですよね。時間を巻き戻すわけじゃないけど、もう一度自分の身近くに手繰り寄せないといけないなって。〝それはとても複雑な問題なんだ”ということも含めて。俺はロックミュージシャンなので、〝戦争反対〟とか〝ラブ&ピース〟みたいな愚直な言葉が好きだし、使いがちですけれど、もちろん、たったひと言では語れない複雑さが転がってるっていう」
古川「福島の中でも、〝反原発〟って即座に言える人は外部の人なのかなって思っちゃうくらい、みんな立場が複雑で、沖縄もそこは一緒なんだろうな」
後藤「沖縄の人間が辺野古の警備をすると揉めごとになるから、外部から人員を連れてきているって話も伺いましたよね。難しいな…。よく考えるんですよね。〝外部の人間〟って言われると、何も言えなくなってしまうところがあって」
古川「問題は、〝外部・内部〟っていう発想を、どうなくしていくかだと思うけどね」
後藤「そうですよね。そのボーダーについても、誰が内部で誰が外部かって、ホントはもう少しグワグワしてるものなんじゃないかなって。僕の中にも沖縄や福島と繋がっている部分がきっとあるはずだし」
古川「想像力を経由することで、当事者になれるような装置は作れると思ってて、それは俺だったら小説だし、ロックにもできると思う。俺はロックミュージシャンは〝戦争反対〟って言っていいと思ってて、それはロックが〝戦争反対〟って言ったときに、当事者の両方に対して言ってるから。両方とも自分たちのロジックがあって、自分たちが正しいと思って戦争をするわけだけど、〝戦争反対〟って言うとそこを崩せる。そういう言葉もすごく大事だし、小説は相手の立ち位置に立たせるっていう装置を作るべきだと思う」
後藤「やっぱり、都合よくボーダーを引く感じがすごく嫌なんです。でも、さっきの話に出たように、戦闘機の音は届くわけで、市の境も街の境も関係ない。ボーダーっていうのは徹底的にフィクションなんだって思います」
古川「嘉手納で思ったことをさらにメタファーで捉えると、目に見えない音が迫ってきて生活を侵食するっていうのは、福島から放射性物質が飛んできて、それは福島だけを飛んでるわけじゃないっていうことに近い。見えないものが境界線を越えて侵蝕していくっていう、似たような現象なんだなって」
後藤「ボーダーは関係なくて、みんなの問題なのに、アウトソーシングしているわけですよね。そういう問題に対して、僕は一緒に抱え込んでうわぁって悩みたい。単純にイエスかノーかで考えるのではなくて、この状況をよくしていくためにはもっと言葉が要る。それこそ、原稿用紙千枚でも足りないくらいの」
古川「よい書き手になるためにはよい読み手にならないといけなくて、結局リテラシーを底上げしていくしかないんだよ。誰かの書いた文章を、正確に、膨らみを持って読めるか。〝AがBでCでした〟って書いてあると、みんなそれをそのまま受け取っちゃうんだけど、実はそれは微妙に違う。言葉って単純じゃないんだってみんながわかってくると、よく読めるようになるし、自分が書くときも、膨らみを持った強い発信力に変わっていくんだろうなって」
後藤「それはとても楽しいし、面白いことなんだって同時にアピールしたいですね。そうなれば、みんなが使う日本語も生き生きとしてくるはずだし、いい作品が生まれる。いい作品が生まれると、世界中で読まれますしね」
古川「リテラシーの問題はすごく重要で、リテラシーがないから、直接的に目に入らないことは想像もできないし、わかんなくていいと思っちゃう。自分の庭のことだったらわかるけど、他人の裏庭なんて想像できない。そこに繋がると思う」
後藤「人が何かをイメージするときって、脳内である種の言語化を行っているんですよね。文字通りの言葉にしなくても、音楽だったら音楽用の言語で言語化しないといけない。想像力って徹頭徹尾リテラシー=言語の処理能力の問題だと思うんです。たとえば、頭の中にありもしない風景を立ち上げるときだって、イメージは脳内で言語のように振る舞います。そういうことを弛まずにやっていかないといけないし、それが人間であることのような気がする」


古川 日出男(ふるかわ・ひでお)
1966年福島県郡山市生まれ。小説家。著作に20世紀の軍用犬たちの叙事詩『ベルカ、吠えないのか?』、世紀末の東京でのテロ事件に手向けられた鎮魂曲『南無ロックンロール二十一部経』など。昨年発表の『女たち三百人の裏切りの書』では野間文芸新人賞と読売文学賞をダブル受賞した。震災直後のドキュメンタリーでもある『馬たちよ、それでも光は無垢で』は仏語訳とアルバニア語訳も刊行され、この3月にはコロンビア大学出版より英訳が発売になる。'13年から郷里の郡山に『ただようまなびや 文学の学校』を開校し、学校長も務める。