私たちは日常的に意識せず、様々なことをアウトソーシングしながら暮らしている。地理的にも遠く離れ、辿ってきた歴史も大きく異なる地域の距離と時間を編み直すことによって、得られるヒントとは。小説家・古川日出男と巡る福島と沖縄。
後藤「この号の記事のために赤坂憲雄さんの東北行脚に同行させてもらったんですけれど、距離や規模というのは、体で感じないとわからないことがたくさんあるなって思ったんです。でも、それって、ツアーをしていて感じることでもあるんですよね。〝日本は思ったより広いぞ〟っていう。そういうことで気がつくのは、普通の暮らしの中では自分の想像力が追いつかないような場所にいろいろなものがあるということで、それは原発とか基地とか、センセーショナルなものだけじゃなくて、たとえば、ゴミ焼却場や火葬場もそう。そういう普段は縁遠い場所に置かれているものを、目の前に再提示するものって、パッと思い浮かぶのは文学だったんです」
古川「なるほどね」
後藤「小説には普段自分が目の当たりにしない暴力的なシーンとかがあって、グワッと一気に痛みや死が迫ってくる。もちろん、読み終わると過ぎ去っていくんですけど、違う熱として身体に残るというか。そう考えると、書いたり読んだりすることって、普段アウトソーシングしているものとの距離感や体感をもう一度引き寄せるヒントになるんじゃないかと思って、ぜひ古川さんにお話を伺いたいと思ったんです。福島と沖縄っていうのは、東京からの距離っていう横軸の問題だけじゃなくて、縦軸の、歴史っていう問題もあります。そこで思い出したのが古川さんの作品たちで」
古川「まず福島で思ったのは、常磐炭鉱(※1)もそうだし、仮設住宅とニュータウンが隣り合わせになった場所もそうなんだけど、時間のレイヤーが一目でわかる場所が多かったのがすごく衝撃的だった。過去を消さないまま、同じ場所に分けて配置されてるっていうのが、とても不思議だなって。日本って基本的にはスクラップ&ビルドの文化だから、歴史的な地方性が全部残ってる場所っていうのは、そんなにないと思う。しかも、あの炭鉱の長屋と、震災以降の仮設住宅には通じるものがある。つまり、震災が起きて新たな問題が出てきたんじゃなくて、震災によって今までずっとあった問題に改めて向き合わざるを得なくなった。そういう場所なんだなって」
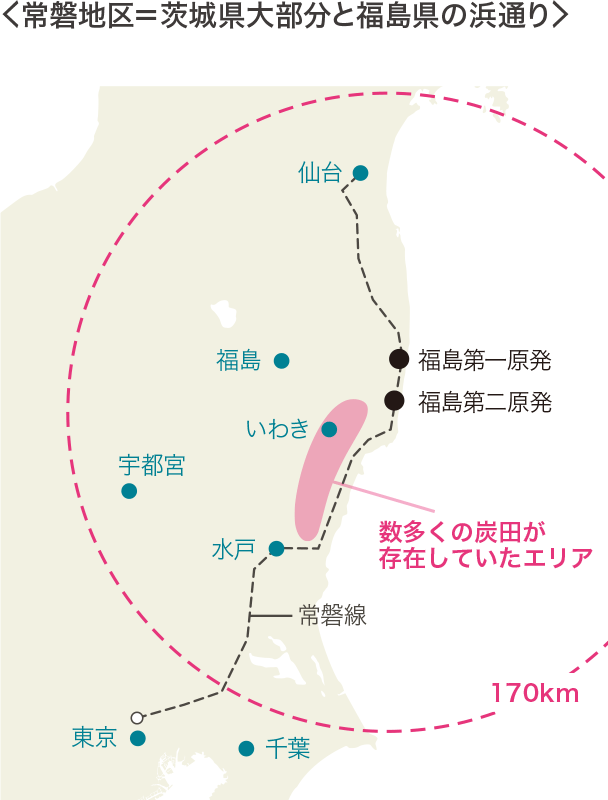
後藤「ほとんどのことがそういう構造だと思うんですよね。東日本大震災で起きた福島を中心とした問題っていうのは、もともと全然他人ごとじゃない。『常磐線中心主義(ジョーバンセントリズム)』(五十嵐泰正・開沼博責任編集)という本には〝東京の下半身〟と書かれていましたけど、これまで常磐地区に押し付けて、見えないようにしてきたものが、ゴロゴロと目の前に転がり落ちてきたっていうだけだと思います」
古川「でも、多くの人はそれを大雑把に読解することしかしたくない。さっき今回のテーマは〝読むこと・書くこと〟だって言ったけど、自分は作家だから、何度も頭の中で考えたり、何度も書き直したり、何度も何度もって納得いくまでやるんだけど、もしかしたら、読むのが一回だけっていうのが今一番まずいのかもしれない。ネット上の言説とかって、一回しか読まないし、しかも自分が気になるところしか読まないから、それで問題が生じる。内郷(※2)みたいな土地を前にしたときに、この現実を読むためには絶対に一回ではわからない。何層も重なってるから何度も読み直さないといけない。一回しか読まないで、〝これはこうだ〟って一緒くたにしてたら、未来はないかなって」
後藤「まさに、これからはそういう行為が必要になるはずです。今日見た景色をただドキュメントとして収めても、下手をすると、いろんな軋轢を深めてしまう結果になりかねないと思うんですよね。でも、それを一旦持ち帰って、別の話として立ち上げると、福島だけではなく、忘れ去られた様々なバックヤードのような場所を、一人ひとりがそれぞれの形で立ち上げることになると思うんです。しかも、このわだかまりをわだかまりのまま投げられる、疑似体験させられるというか。書くことにはそういう力があると思います」
古川「震災直後の一年くらいは、〝これは見えない恐怖だ〟ってみんな言ってたでしょ? 放射能は目に見えないって。でも、それがだんだん見えるものに転化っていうか鈍化、典型化していって、出発点が忘れられた気がする。見えないものを扱っていろんなことが起きたんだから、それを表現するには一回全然フォームを変える必要があって、それをみんな忘れちゃってる」
後藤「放射能が見えないことって、現代人に対する皮肉にも感じますよね。比喩として、〝お前らには見えていないんだ。これから先も見えないぞ〟っていう。だからこそ、もっと目を凝らさないといけないし、もっと考えないといけないと思うんです」
古川「数値っていうのはいい面も悪い面もあって、ベクレルとかシーベルトっていう単位で数値がわかるから、どこが安全か何となくわかって、目に見えるものだと思っちゃう。でも、〝もともと見えないじゃん〟っていうのが忘れられてる気がする。それに対しては子供を持つ親が一番ビビッドに反応してて、〝県外へ避難する〟とかってなるから、そのときに内部と外部の対立が起きるんだけど、そこで問題なのは数値みたいなファクトの話じゃなくて、愛の深さの話でしょ? そういうことは誰も言わないよね。愛ゆえに自分が子供の立場になっちゃうから、実際の子供が恐怖する以前に、自分のほうが恐怖してる。それはファクトとは別のところで包摂しなきゃいけないことで」
後藤「それは想像力の問題とも言えますよね」

古川「そう、想像力を使って炭鉱跡の景色を読み直すと、あそこは未来なんですよ。炭鉱跡の長屋に見たものは、震災以降にできた仮設住宅の姿であって、原発事故の問題っていうのは、炭鉱で起きたことをもう一回やってるってことだから」
後藤「炭鉱の労働者のための長屋と仮設住宅の間に何があるのかを書くのが文学だと思んですけれど、今日見てきたことをすぐ言葉にできるかっていうと、それはできない。でも、何か近しいものを感じたわけじゃないですか? 今のところ、実際に誰かを案内するしかそれを伝える方法はないんだけど、でもきっと、書く方法がある気がするんです」
古川「俺はもともと未来も過去も現在もシャッフルして小説を書いてきたわけだけど、原発事故が起きて、実際に時間がシャッフルされた気がしてて、今回炭鉱跡を見て、やっぱりそうなんだって思った。そういうことって忘れちゃいがちで、何かが起こっても時間が経つと〝昔はよかった〟とかってなっちゃうんだけど、でもあのシャッフルされた感覚を忘れないようにすることが、音楽とか文学の役割だと思う」


古川 日出男(ふるかわ・ひでお)
1966年福島県郡山市生まれ。小説家。著作に20世紀の軍用犬たちの叙事詩『ベルカ、吠えないのか?』、世紀末の東京でのテロ事件に手向けられた鎮魂曲『南無ロックンロール二十一部経』など。昨年発表の『女たち三百人の裏切りの書』では野間文芸新人賞と読売文学賞をダブル受賞した。震災直後のドキュメンタリーでもある『馬たちよ、それでも光は無垢で』は仏語訳とアルバニア語訳も刊行され、この3月にはコロンビア大学出版より英訳が発売になる。'13年から郷里の郡山に『ただようまなびや 文学の学校』を開校し、学校長も務める。
■注釈
(※1)常磐炭鉱
福島県の富岡町から茨城県日立市までに広がって存在した常磐炭田には、多いときには130あまりの炭鉱が存在した。
(※2)内郷
福島県いわき市の内郷駅付近の地域。常磐炭鉱の中心地で、炭鉱の町として栄えた。
