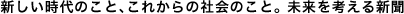『The Future Times』の第3号の特集は『農業のゆくえ』。滋賀県の面積に匹敵する耕作放棄地を抱える日本。エコでもロハスでもなく、農業というレンズで現在の社会をのぞき見ようというのが、今回の特集のテーマです。
——東日本大震災において甚大な津波被害を受けた仙台市、荒浜。一軒の農家の協力によって始まった稲作体験プログラムは今、東北の地でできることは何かを私たちに問いかける——

宮城県仙台市荒浜地区は、平地としては過去に例を見ないほど甚大な津波被害を受けた。この地で専業農家を営む、遠藤喜一さん(56歳)と耕太さん(31歳)。
親子二代による「遠藤農園」は、地区一帯をゼロから再構築したいという想いを胸に、レタスなどの野菜を中心とした栽培を行なっている。
本紙創刊号では、東京・世田谷にある『自由大学』の卒業生を中心としたメンバーが、定期的にその農園を訪れ、農地の復旧を通して新しいコミュニティを作っていく様子を伝えた。
「瓦礫撤去のボランティアといった直近の活動だけではなく、この先も長く継続していけるような、東北被災地との関わり方を新たに作っていきたい」
そう語っていたメンバーたちの表情からは、確かな復興への息吹を感じた。その後も遠藤農園と彼らの交流は続き、昨年末には東京と仙台で並行して被災地支援を行なう『復興クラブ』というコミュニティが立ち上がった。
そしてこの5月、復興クラブは新たなプログラムを企画した。〝稲作サポート〟と題された、その試み。東京で暮らす農作業を経験したことのない人々が、稲作のプロでもある遠藤さん親子の手ほどきを受け、田植えを行なうというものだ。被災地での農作業を通じて、参加者たちはいったい何を感じるのだろう。

遠藤耕太さん。荒浜での『復興クラブ』の活動にとても協力的で、若者目線でともに取り組んでくれている。

稲作サポートは取材の前月から実施。最初の苗はビニールハウスで育ち、田へと植えられる。
仙台駅からバスで30分ほど走ると、遠藤農園のある市の東部沿岸、荒浜地区に到着する。風はなく、5月の穏やかな日差しが心地いい。
「震災後、初めて東北に来ました。被災地のために何かしたい、でも、何をすればいいんだろう……なんて考えているうちに1年が過ぎて。けれど、やっぱり自分から何か行動しなくてはと思って応募しました」
作業を前にしたオリエンテーションで、参加者のひとり、石井修平さん(29歳)はそう話した。
メンバーは男女あわせて8人。24歳から35歳まで、比較的若い面々が集った。普段は出版社に勤める石井さんをはじめ、商社の事務やSEなど職種はバラバラだが、彼らには、共通して抱える思いがあった。
「募金や物資は送ってきた。でも、本当はもっと直接的に被災地と関わることのできる場所を探していた」
被災地の人々との交流や、一緒に〝考える〟時間を重視する復興クラブの活動は、支援の第一歩を踏み出そうとする若者たちの背中を押す。
遠藤農園の周囲に広がる、見渡す限りの田園地帯は、一瞬にして大津波に飲み込まれた。かんがい灌漑用のポンプシステムも完全に破壊され、水田は排水機能を失った。震災から1年以上経過した今も、海水や雨水が溜まったまま放置されている状況だ。
自分たちの水田にはしばらくの間、手をつけることができない。遠藤さん親子は、津波被害が少ない内陸地域の田んぼを借り、稲作を再開することにした。



荒浜一帯は壊れた道路がそのままの姿で残る
オリエンテーションを終えた参加者たちはいよいよ水田へ向かう。持参した長靴を履き、あるいは裸足で、それぞれが新米の苗をたずさえ、田んぼの中へおそるおそる足を踏み入れる。
「えっ、田んぼってこんなに深いの!?」
「沈む!長靴の丈が足りない!」
「裸足で入ると気持ちいい!!」
飛び交う第一声。初めて味わう水田の感触に、都会の若者たちは興奮を隠せない。そして、ぎこちない手つきで、苗を一つひとつ、土へと植えていく。
「そんなゆっくりやってたんじゃ、日が暮れるよ!」
遠藤さん親子は、なかば呆れ顔で笑いながらも、手植えの作法や米づくりの面白さを熱心に伝える。
その様子は、さながら〝授業〟のようだった。