東日本大震災から1年以上の月日が過ぎました。被災地と一言でまとめてしまうことのできない、様々な “現在地” 。私たちの日々の生活も、例外ではありません。『THE FUTURE TIMES』第2号では、未来に向かって、それぞれの “現在地” を考えるための言葉を集めています。――今回は、震災以降もアートや建築というジャンルの垣根を飛び越え、積極的な活動が注目される坂口恭平さんのインタビューを、創刊号からの続編として、スペシャルバージョンで届けします。

後藤 「このゼロセンターの家屋は、どんな契約で借りているんですか?」
坂口 「最初、15,000円ていわれたんですけど、30,000円にしたんです。俺の場合は、“太っ腹感”ていうのが重要ですから(笑)。 なんでもやっていいですか?と最初に聞いたら、なんでもやっていいですよって。そして期限もない」
後藤 「坂口さんは“なんでもやっていいよ”って言われることが多いんですか?」
坂口 「うん。でもまあ、田舎の場合、それでも住む人がいないから。みんな自分のところがもうあるし。だって、地元で実験的なこととかやらないでしょ?そういう意味では田舎には隙間がある。自分でちょっとずつ作らなきゃいけないのが大変だけど。東京って、自分が何もしなくても娯楽があるし文化もあるし。熊本自体は、可能性はあると思いますよ。ここは自然もあるし。普通、本州の人が九州に来ること自体がめずらしいでしょ。そういう意味では今回のゼロセンターは、きっかけとしてはよかったかもしれない。でもやるからには面白いことやりたいですけどね」
後藤 「今までの坂口さんの著作では“家はいらない” 、“家を所有することでしばられてしまう” というような記述があったと思うんですが、実際、この場所で生活を営んだり、逃げてきた人を助けたりするに際して、家のような場所が必要なんだと思い直されたというところが、とても面白いと思っていて」
坂口 「家っていうよりも、僕は“プライベートパブリックだ”って言っているんです。公共施設とか公共機関って僕は信用できなくて。だって公共施設って建築家が税金使うために作っていて、大きな建設施工業者にお金が流れていく仕組みじゃないですか。ただ、全部がそうじゃなくて、金沢の美術館とか行くと違うなって思うし、成功しているところもある。けど大半の公共施設は税金を使うために作られているんだろうなって感じてしまう。そういう建物が必要かどうかって市民の誰にも聞かないわけですから。それで、建築家っていうのは、大きいもの作った方がお金をたくさんもらえるから、そういうコンペにみんなで勇んで向かって行くわけでしょ。そういうものでしかないパブリックなものに対してどうにかしたいっていうのが、今回の提案なんですよ。僕は“家が必要ない”って言っていたわけじゃなくて、何故あのおじさん達の家(※1)が小さくて安いもので済んだかって言う話をしてきていたわけです」
後藤 「なるほど」
坂口 「それは何故かといえば、町自体を家の一部として利用していたんだと。僕達はプライベートな持ち物を購入し、ここは壁でおおって見せないようにして、公共の道を歩きながら買い物をして暮らしている。でも、そういう家じゃなくて、隅田川の鈴木さんの家(※1)は小さくて、一間(いっけん)くらいなわけです。でも、彼にとっては街の図書館が自分の書庫、公園のトイレがプライベートなトイレ。お店から捨てられるものを少しずつ採集して、ガソリンスタンドからは電源をもらって利用する。そうすると、彼が実践していたのは“家がいらない”んじゃなくて、“ここもあそこもわたしの家である”ってことなんじゃないかと。そして、そういうのを僕達が見ていると、“ここは私の空間である”という考え方が少しだけ揺らいでくるんじゃないかなと」
後藤 「面白いですね」
坂口 「従来の考え方だと“大きな家を建てる”という方向に言ってしまうところを、家自体はすごく小さくてよくて、近所にすごくいいレストランがあればそこが自分のキッチンみたいな…。そういうふうに捉えはじめたら、レストランも“これいくらで出すよ”とかっていう、単なる売るためのものじゃなくなるかもしれない。もうちょっとお客さんと提供する側との人間同士の関係になるっていうか。ここでコーヒーを飲むとおいしいとか、もう少しその人のリビングに近づけるような。なんとなくこういうのは理想的すぎて飛躍した話だと思っていたんだけど、鈴木さんは既にそれをやっていた。だからびっくりしたんです。鈴木さんは僕のレイヤーで言えば “超豪邸に住んでいる”って僕は言っていたんですよ。しかも、彼らは“所有”をしている」
後藤 「はい」

坂口 「“所有”っていう概念を僕は消したいわけじゃなくて、“あそこの場所は俺のもの”って思っている限り、それは“所有している”ことになるということ。でも、その“所有”は奪われたときに“まあしょうがねえか”って思えるものなはずなんですよ。だって、その場所に対して、なんらかの契約をしているわけじゃないから。アルミ缶だって“このおばちゃんからもらう”って鈴木さんは決めていて、ある意味では所有しているんだけど、彼より早い時間に他の人が来てしまって奪われてしまうこともあるわけです。そういうときに“あ、失敗したな”っていう感じがある。僕はそれを見たあたりから“所有”って言葉を使うようになってきたんですね」

坂口 「熊本にきて、このゼロセンターの建物自体を一瞬買いそうになったんですよ。これを買って完全な公共空間みたいなものにできないかって。でも、所有するのはコンセプトとずれるので、考え直して。僕はここで仕事もするんだけど、同時にパブリックな場所にもしたかった。個人が作るパブリック空間、“プライベートパブリック”として、ゼロセンターを1回作ってみようかと。だから、アポイントなしで人が来ちゃう。半分公園ですからね。もちろん、こっちも仕事してんのにと思うこともあるから、喧嘩もするんだけど(笑)」
後藤 「それはみなさん、感覚として理解して、ここへやってきているのかな?」
坂口 「そうですね。けっこう面白いですよ。例えば自分はマッサージができるから避難した人に施術を提供しようとか、こういう余っている土地があるから食料を作るための畑にしたら、とか。だから僕は今、阿蘇と大牟田と二カ所の畑を持ってます。菜種油で機械を動かす仕組みを作っているからその技術を持ってきたい、という人とか。そうなると、じゃあ、畑で菜種を作ってみようか、とか。みんな私はこういう技術がある、って言って、集まってくる」
後藤 「良いですね」
坂口 「そうやって自前でやればいいんですよ。その場合、ポイントなのはコントロールされているということを自覚すること。必ず、何かにコントロールされているわけですから。でもそのコントロールしているのが誰かってことは見えにくくなっている。だから電気がどうなるかとか、あと、住宅の件もそうですけど。30,000円で作れる家だってあるのに、安く家なんか作れないと思わされている。でも農地がちょっとでもあれば、その横に工作物作ることなんて、全然できるわけですよ」
後藤 「はい」
坂口 「寝ているときは中でいいけど、だいたいは外に出ようと。路上生活者の生活を見ていても、“外にでようよ”というのはひとつのテーマなんですね。外に出なきゃいけない。都市っていうのは、人が外に出て動きまわることによって動く。でも今、みんなすぐに中に戻って行っちゃうので、だから日本の町が面白くないんだなと。アフリカの町がなんで面白いかっていうと、人がずっと外に出ているんですよ。そうすると、人が表に出ている分だけ町っていうのはほつれていきますから。今の日本ではなかなか見えにくくなっているけれど、でもあるんですよ、日本にもね。これまでも僕は、そういうものだけを日本の中で見つけ出してきたつもりですけど。ここは、そういうものを伝えるための起動装置にしたいと思ってる」


坂口恭平(さかぐち・きょうへい)
1978年熊本生まれ。建築家、作家、アーティスト。早稲田大学理工学部建築学科卒業後、日本の路上生活者の住居を収めた写真集『0円ハウス』を刊行。06年にカナダのバンクーバー美術館にて初個展。07年にはケニアのナイロビで世界会議フォーラムに参加。著書に『TOKYO 0円HOUSE 0円生活』『隅田川のエジソン』『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』ほか。東日本大震災後に熊本市へ移住。自ら「新政府初代内閣総理大臣」を名乗り、同市内坪井町に「ゼロセンター」を5月に設立した。
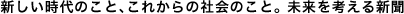

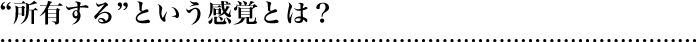
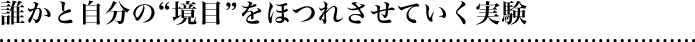


※1『隅田川のエジソン』(青山出版社刊/1365円)
隅田川の河川敷に住む実在する人物“鈴木さん”をモデルに、坂口さんが2008年に発表した小説。この“鈴木さん”に学ぶ0円生活について書かれた続編とも言える実践書が
『TOKYO 0円ハウス 0円生活』(河出書房新社刊/798円)。