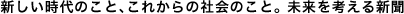控え室にて
――今日は南相馬からイベントに参加していただき、ありがとうございました。
上野「いえいえ、どういたしまして」
――あらためて、この3年間を振り返ると、どんなことを思われますか?
上野「早いような、短いような。でも、あっという間だったかな。震災後の9月に生まれた倖吏生が、もうすぐ3歳になるんです。亡くなった倖太郎があのとき、3歳だったんです。話す内容なんかが似てきてね。それがね……」
――後藤さんは、「東京のスピードは、復興っていう字すら置き去りになっている速度を感じる」と言っていましたが。
上野「当事者かどうかで、スピードの違いを感じるのは当然だと思います。あんなことがあったんだ、みんな善人になれ、もっと自粛して慎ましく生活しろなんてことは、一切思わない。ただ、今ある日常が当たり前だとは思わないでほしい。親にとって、子供を救うのが一番の仕事です。私は、それができなかった。なぜ助けられなかったのか、今でも悔やみ続けています。もっと愛情を伝えたかったと今でも思いますし、親父にもお袋にも苦労ばかりかけた。なぜ、もっと『ありがとう』という気持ちを伝えてこなかったんだろうと悔やみます。たぶん、どんなに後悔しないように家族と日々接していても、家族を失った時、後悔をゼロにする接し方なんてない。だからこそ、いつ何が起きても、できるだけ少ない後悔ですむような接し方を家族としてほしいです」
――「今は笑って、天国から見ている人たちを安心させたい」と仰っていましたね。
上野「去年くらいからそう思うようになりましたね。人は弱いです。自分の力じゃない。みんなのおかげで、やっと笑えるようになったんで。ただ僕の気持ちをどう説明していいか……。僕は、明日死んでもいいんです。あの日以来、もう生への執着ってものはなくて。死ぬ瞬間に笑っていられるように、今を精一杯走り切れば。だから繰り返しになりますが、もし、3年前に何が起こったのかを忘れかけている人がいるのなら、今の自分は恵まれているんだということを、幸せを、噛み締めながら生きてほしいです」
――“3年後の現在地”、佐藤さんには、どう映っていますか?
佐藤「震災から1、2年目は、都会と東北の差異に憤りを感じることが多かったんです。都会の人に『なんで楽しめるの?』って。ただ僕自身、震災後に出会った人たちに支えてもらったり、考え方を変えてもらったんです。3年経った今は、人それぞれのペースがあるんだなと思えるようになりました。震災や東北と向き合うことって、当事者以外は勇気がいることだと思うんです。忘れているというより、無意識的に目を逸らしている部分もあるのではと思うんで。ひとりで向き合うということは、恐怖でしょうから。だから、向き合いたいと思ったタイミングで、向き合い続けている人がいるということが、東北との間口であり、きっかけになると思っていて。だから僕は、語り続けようと思うし、写真を撮り続けようと思います」
――なるほど。
佐藤「もちろん、復興のこれからに、社会や日本のこれからに、絶望しうる材料はいくらでもあるし、同じくらい可能性の材料もある。でも自分以外の人に、こっちの道が正しいでしょって強制する気は全くなくて。正しいと思っても、現実や自分の生活を鑑みて、『そっちには行けない』と思う人もいるかもしれない。そんな人のためにも、『じゃ、俺はこっちの道を行ってみるよ』と進んでいきたい。どんな選択をしようと、大切なことは、“自分なりの気持ちよさ”を見つけることかなと思うんで。いろんなことを知り、見て、会って、コミュニケーションを取って、自分が何を感じたら気持ちいいのか、何を感じたら気持ち悪いのか、それを知ることが大事で。それが自ずと、自分自身と向き合うこと、歩んでいく道を探すことに繋がると思うんです。もしも、その答えが自分とは違う人がいても、他者の幸せを認める。そして何より、自分にとっての幸せだとはどんな状態やどんなことなのかを知るということが、何より大切だと思います」
――“3年後の現在地”、安田さんには、どう映っていますか?
安田「今日のイベント、客席のみなさんは本当に真剣に耳を傾けてくださいました。あらためて、多くの人が、東北に関心がないのではなく、間口を欲しているんだなと実感しました。だから、私も伝え続けることを諦めてはいけないなって」
――ゲストの木村さん、上野さんを始め、何より当事者の方々が諦めていませんよね。
安田「そうですね。私は陸前高田の取材を多くさせていただいているんですが、あれ程の津波を経験し、現地の人は『海を恨んでいるだろうな』と最初は思っていたんです。でも、漁師の方々は海に戻っていく。お孫さんに『じーちゃんの獲った魚が食べたい』と言われ、漁を再開された方もいました。今も、多くの人が、宝物を取り戻そうとしている最中です。人がいる限り、諦めない人がいる限り、町は死なないと思います」
――ただ、都会と被災地のギャップなようなものに、苛まれたりはしませんか?
「もちろん葛藤のようなものはありますが、これが現実だよと突き付けるのではなくて、人は当たり前だと思っていることが、当たり前ではなかったという体験をいくつできるかで変わるのだと思うんです。今回の写真展を訪れ、『私には何も出来ない』と思っていた人がいたとしても、家族や、友達、恋人に、今日から少しだけでも優しくしてみようと思うだけで、それは変化だと思うんです。私は取材を重ねる度に、人の絆というものを強く感じます。人を救うのは人です。私は人間の力を信じています」――“3年後の現在地”、渋谷さんには、どう映っていますか?
渋谷「正直、まだ闇の中というか。『これ以上、何があったら人は変われるのか?』という絶望感のようなものはあります。ただ、誰よりも当事者たちこそが諦めていない。だから、希望ではなく可能性は絶対に残されていると思うんです」
――その可能性とは、たとえばどんなことを指すのでしょう?
渋谷「木村さんが、世界や社会を変えるために『向き合うのは自分自身』ということを仰っていましたよね。まさにそのとおりだと思っていて。足下に堆積する過去の上に、今の私たちは立っているわけです。難しく考える必要はなくて、ひとりひとりが『今日、こうありたいと思った自分に成り得ているか』と、足下を見つめ直すことが大切だと思います」
――ただやはり多くの人にとって、多少の後ろめたさこそあれど、震災は風化しつつあるのが現実な気もします。どうすれば渋谷さんたちのように、関心や熱量を維持し続けることができるでしょう?
渋谷「私の場合は正直に話すと、正義感に突き動かされて東北に携わったわけじゃないんです。20年前に、阪神淡路大震災が起きました。その時、私は関西にいたのに何もできなかった。その後悔に背中を押され、いても立ってもいられずに現地に入った結果が今日に繋がっています。東日本大震災が発生し、『ここで何か出来なければ、私はもう写真を撮り続けることはできない』と。トークイベントで安田が『震災の間口が時間と共に小さくなりつつある』と言っていましたが、誰にでも、いつでも、必ず変われる瞬間が訪れると思います。繰り返しになりますが、『今日、こうありたいと思った自分に成り得ているか』ということを誰もが考え、未来を志向することで、結果として社会が変わるという可能性があるのではないかと信じています」
――イベントが無事終了しました。木村さん、上野さん、そしてフォトジャーナリストの3人のお話を聞きし、あらためて、人によって“3年後の現在地”というものにギャップがあると感じました。
後藤「思っていた以上に、世間の興味が薄れるスピードが早い気がします。志を持っていても、世の中の流れに抗うのは難しいんだなとも思う。ただ難しいのはわかっていても、忘れちゃいけないことがあるんじゃないかなと思います。『本当にこれでいいのかな?』って立ち止まって考えてみることも大切だと思いますね」
――今日のイベントは、昼、夜共に多くの方が来場されました。世の中の速度に抗うことに『THE FUTURE TIMES』が寄与している手応えもあるのでは?
後藤「手応えというのは正直わからなくて。与り知らないとも言えるかもしれないけど。創刊した時から思っているんですが、花を見るのは僕じゃなくてもいいと思っていて。僕らは種をまき続けるだけというか。僕らの活動をきっかけにして何か果実が実るのだとして、それを収穫するのは、新聞を読んでくれた人の下の世代、子供の世代で良いと思っています。それでも誰かのためにという想いがあって。今は新聞を作ることで、虚無に陥ったり、絶望したりしないだけでも救いなのかなと思ってます」