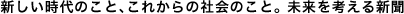渋谷「今、木村さんは、娘さんと白馬に暮らされていますよね。ペンションを購入して、電気に頼らない、大量生産大量消費、いろんな言い方はあると思うんですけど、お金や経済に傾きがちな社会の価値観とか、言葉にすると難しいんですが、木村さんはそうじゃない、今の国の目指す方向、経済の目指す方向ではない、別のベクトルで実験的に“深山の雪”というペンションをされていますよね」
木村「そうですね。正直、原発の幹部の方々には怒りを覚えるんです。でも、そうじゃなくて、原発を動かしてるのは我々ですよね? 我々の生き方を変えていかないと、世の中って変わっていかないと思うんです。それにはどうしたらいいかって考えた時に、電気に頼らず生きていける方向に行けるような生き方をまず自分が実践して、そこに人を集めて体験してもらうのが自分に出来ることなのかなって思って。必死に働いてお金を稼いで生きていくんじゃなくて、生きるために体を使って、できるだけ身の周りにある物で生きていくと。地産地消じゃないですけど、それに近いような状態で、完璧にはムリだと思うんですよ。今すぐに完璧に、お金の介在しない生活をするのはムリだと思うんです。自分でも無理です。でも、それに少しでも近づいていければ、世の中って変わっていくと思うんで」
渋谷「後藤さんも、以前、『変わるべきは、まずは自分』ということを仰ってましたよね。それは僕も思ってて。慧ともそういう話をよくするんですが、やっぱり世の中を変えるって、なかなか難しいですけど、まずは自分の見方を変える、考え方を変える、まず自分から変化そのものになっていくというのが、一歩目なのかなと思うんです」
後藤「『上にいる誰かが変えてくれる』と思うのでは、それはまた別の大きな権力を担保するだけなんですよね。それでは封建社会なんです。自分はミュージシャンで、僕のような職業の人間には多くの人にいろいろなことを語りかける拡声器のような機能があるので、それを使って新聞をやろうって思ったんですけど。いろいろな人の声を僕という拡声器を使って、広く伝えようって。でも、『結局、どうやって世の中を変える?』って言ったら、新聞を持って帰ってくれた人たちに、それぞれの場所で少しずつ変わってもらうしかない。 “経済”が行き過ぎている社会を変えるには、お金の使い方を変えるしかない。お金は物と物のやり取りを潤滑にするために生まれたんだと思うんですけど、でも、貨幣価値という物差しがすべての価値を計れるかのような振る舞いをしている。たとえば、自分の音楽がいくらかって、僕にはまったく分からないんですよ。強いて言うんだったら、スタジオ代やプレス代がこのくらいかかったから、逆算してCDの値段はこのくらいって。それってCD一枚として、製品の値段としてしか決められなくて……。本来的には、音楽って一曲いくらですかって言っても、分からないんです」
佐藤「本の値段だって、紙代、プリント代ですよね。でもその価値って、本当は一人一人が決めなければいけないはずなのに、つけられた物差しだけが正しいと思ってしまう」
後藤「その順序が間違っているっていうのは、すごく思います。先に人間とか、人の行いがあって、そこに対して、上手にやり取りしやすいように貨幣という発明が乗っかってきたのに。そういうところは、みんなで取り戻していかないと。そうしないと結局、『最終的にすべてをお金で計るの?』っていうところに、社会が行き詰まってしまうと思うんです」
渋谷「無自覚のうちに、奪われていったのか、失っていったのかわからないんですけど、震災後、何か気づきがあったのなら、そういうものを取り戻していくっていうか。生きていく力みたいな物を木村さんからも感じるんですよね。これだけ取り返しのつかないことが起こったのに、それでも木村さんはそこから、何かを取り返そうとしている。木村さんのペンションに行くと、それが少し目に見える形で見える。木村さんのペンションにはストーブがあるんですけど、ロケットストーブと言って。木村さん、説明してもらっていいですか?」
木村「はい。ロケットストーブというのは、元々は難民キャンプなどで煙の害を防ごうという目的で、アメリカの教授が考えたものなんだそうです。火を燃やした時に煙が出ますよね。その煙をもう一度燃やして、できるだけ煙を少なくして外に出そうというシステムのストーブで。そのストーブ自体も、どこにでもあるような廃材で作れてしまったりするんです。うちの場合でも、2、3万円で立派な物が出来ました。でも、それを使いこなすには、非常に手間ひまがかかって大変で。そもそも、火を自分でおこすというのは大変で、ススも出るし、手間がかかる。でも、その手間を楽しいと思うことが出来れば、そこにお金は生まれないですけど、それこそ豊かな生活なのではないかと思うんです」
渋谷「火をおこすって、案外やったことないんですよね。特に東京では、公園でたき火をすることも出来ない。それを、家の中でやるってことですよね。それはすごく、手触りというか、火の暖かみを直に感じることが出来る。もうひとつ、僕が木村さんに見せていただいたのは、鹿の解体、山で捕まえた鹿の解体をするワークショップもされていますよね」
木村「長野県は、年間3万6千頭くらいの鹿が駆除されているんです。その中で、肉として売られているのはわずか1500頭くらいで。6000頭くらいは猟師さんが自家消費しているんじゃないかなんて話もあるんですが、それでも、その多くはゴミになっているんです。まだ山に捨てられるのならば、自然に帰るということになるかもしれませんが、燃やされたりしている。その反面、お金を出せば、スーパーで美味しいお肉が買える。元々、私は福島県の富岡町というところで養豚業をやってたんです。豚を育てるのに莫大なエネルギーを使い、結果、スーパーに行けば簡単に肉が買える。だけど一方で、長野県の鹿のようにムダになっている肉があるんです。それを考えた時に、ああ、こういうことなんだなと。同じようなことが他にも沢山あります」

安田「今、渋谷が言った“手触り”や、木村さんの仰った鹿の解体で思うのは、『THE FUTURE TIMES』の6号で記事を書かせていただいたんですけど、陸前高田の漁師さんの取材を私はずっとしていて。そこで私は、魚を絞めるということを初めてしたんですね。タコって、魚介類の中では珍しく痛点があるんです。キュッてしてみると『ウッ、痛い!』ってリアクションをするんですね。でも、それを経ることによって、手触り、“自分は命をいただいている”っていうということを取り戻しているような気がして。漁師さんたちも自覚しているんですね。『漁師というのは命を懸けている仕事でもあるし、命を取っている仕事でもある』と。そこには先ほど出た、お金では計れない価値観がそこにあって。震災の後、そういった価値観を取り戻そう、取り戻そうって、多くの人がしていた気がするんです。それが、時間とともに間口が小さくなっていっている。でも、決して今からでも遅くはなくて、たとえば今日のお話を聞いた皆さんが、『じゃあ、木村さんのところに行ってみようかな』とか、間口さえ見つけることが出来れば、きっと求めている人は沢山いると思うんです。私も、いつか白馬にお伺いできたらなと思ってます」
木村「ぜひ。今、田舎暮らしに憧れている人が沢山いると思うんですけど、突然、田舎に行って生活するっていうのは難しいと思うんです。予行練習じゃないけど、ちょっと家に来て、そういう体験をしてもらえれば」
佐藤「そういった体験を、ストイックに自分を削ったり、現実から逃避するわけではなく、楽しんでやっていきたいですよね」
木村「そうです。楽しまないと続かないと思うんで。そこは僕自身も楽しんでやっていきたいなって思います」

佐藤「僕はアフリカのザンビアという国に1年間くらい暮らしていたことがあって。電気も水道もない場所で、自分で肉も締めるし、自分で色々なものを作らなければいけないんです。でも、それって苦労じゃないんですよね。お金を出して買うということは、確かに簡単に物が手に入るかもしれないけど、自分で何かを手に入れるという喜びを失うということでもあるのかなって思ってまして。数週間日照りが続いて、井戸が乾いてしまった後の雨なんて、メチャクチャ本当にありがたいもので。そういう肌感覚みたいなものを、ドンドン取り返していかなければいけないのかなって思いますね」
後藤「都市って、元々そういうものですもんね。歴史の本を読むとわかるんですけど、都市化することで人々は“死”っていうものを、どんどん都市から、自分から、外に出していったんですよね。自然に対する恐怖心と同時に崇拝心みたいなものをどんどん外部化して、街って大きくなっていった歴史があるので。畏怖が外部化されて、“穢れ”になっていく。そういうところでやっぱり都市生活者っていうのは、忘れているところがあって。何もかもあって当たり前っていうか」
安田「おそらく今回の写真展も同じようなことが言えると思うんです。木村さんの写真をご覧になった方が帰り際に言った言葉なんですけど、『自分は東北に対して何も出来ないかもしれないけど、今日家に帰ったら、いつもティッシュ箱でパコンって叩いたりしてる息子に、コンって少しだけ優しくしようかな』って。あ、それなのかなって思って。やっぱり東京で暮らしていると、どうしてもこう、今ある日常が決して当たり前じゃないっていうように思える機会ってドンドンドンドン減っていると思うんですね。震災の時は、やっぱり身近に当たり前のようにあるものでも、あっという間になくなる可能性ってあるんだってわかったはずなのに。やっぱり時間が経つとともに、そういった感覚って風化していって。そういった感覚を日常の生活の中で、何かリマインドするような機会、たとえば命をいただくというようなことも、それに近いことだと思うんですね。命というものは、いつか失われるもので、自分たちは、それをいただきながら生きている。やっぱり、命に感謝しながら生きていかなければいけないっていう感覚を、もっともっと日常の中に組み込めればいいのになって思いますね」
後藤「なんか、食っていうのはひとつの例えになると思いますね。要は、“想像力の射程”がみんな短いんじゃないんですかね。“子供や孫の世代”とかいう時間的な射程だけではなくて、たとえば人のことを考えたりしないでインターネット上で発言するわけじゃないですか。こんなこと言ったら人がどう思うだろうとか、そういう想像力や思いやりみたいなのはどんどん減ってる気がして」
渋谷「写真展を見ている人を後ろから見ていると、真剣に向き合ってくれている。たぶん、見ていると痛かったり、苦しかったりすると思うんです。でもその分、家に帰って、少し優しくなれたり、『ありがとう』って言えたり。人との関係っていうか、後藤さんが言った射程って言うんですかね、少し変わっていく。写真を撮るって、そういう仕事なのかなって思ったりしますね」
後藤「ホントに、いろんなところを取材させてもらうと、いろんな人のいろんな想いがあって。うん、そういったものをみんなで認め合うようなね、社会になっていくといいなと思うんですけどね」
佐藤「そうですね。僕は同時に、“簡単に理解できたと思わないほうがいい”と思うんですよね。被災地、被災者と区切って、僕たち無意識に安心しようと思っていると思うんですが、被災者って言葉なんかじゃ区切られる人なんていないですし。僕らの世界にある物って、辞書に載っている物だけじゃない。人間の歴史に記されているものって、地球の歴史から言ったら1%にも満たないわけじゃないですか。僕らの想像力って全然尽きてないはずなのに、理解したつもりでいると、想像力を閉め出してしまうんじゃないのかなって。簡単に絶望も出来てしまうけど、本当は理解できないものがあるということを自覚することが、希望に繋がるんじゃないのかなって思ってるんです」
後藤「本当にそうなんだよなあ。思い合うのが一番いいんじゃないかと思うんですけどね。自分の理解というか、範疇を越えたものに出会うと、急に攻撃し始める人とかいるじゃないですか」
佐藤「そうですね。自分の目で見て、感じて、人と会ってコミュニケーションして、それで衝突するのはいいと思うんですね。意見が人それぞれ違うのは当然のことだし。でもたとえばネット上で、見もしない、確認したわけでもないのに、それが暴力的だったりした時、ギスギスした感じというか、そういったことの加速度が、ますます増してるなってのは感じますね。漠然とした言い方ですが、逆の方向に向かっていきたいなと思いますね。木村さんもまさにそういう方向で、共感する部分がありますね」
後藤「そうですね。震災から3年が経って、沸々と憤りが再燃するというか。どうしてこんな不条理を、そのままにして社会は進むんだろうって。だって自分が住んでいた町に戻れないことなんて、本来あってはならないですよ、絶対。そんな権利を奪われるなんて、やっぱり今でも信じられないことで」
渋谷「そのことで言うと、木村さんの自宅っていうのは原発から3kmほど南にあるんですけど、中間貯蔵施設という、除染で剥ぎ取った汚染土を一時的に保管しておく施設を作るんですね。その施設の予定地の中に、木村さんの家も含まれているんです。もし、それが出来てしまうと、木村さんは汐凪ちゃんを探し続けるのがどうなってしまうのかなと不安で」
木村「今はまだ結論は出てないんですけど、これから住民説明会があって、どう計画が進んでいくのか決められていくと思うんですけど。自分としては、国が土地を買い取るよってなったとしても、売る気はないんです。もしかしたら、それが強制的なものになるかもしれないんで、そうなったら自分としては戦っていかざるを得なくなってしまうんですね。そうならないことを祈るんですけど、現時点では、ちょっとわかんないですね」
後藤「そういうところでもまた、“お金があればいいのかよ”って話ですよね」
渋谷「何が一番大切なのかっていうことを、木村さんの立場で想像してほしいなとは思うんですよね」
木村「あの場所に貯蔵施設を作る理由は理解できます。あそこから汚染土を外に出さないための施設を作る。外には出しては行けないものがあるということはわかるんですよ。実際に、帰れないなら売ってしまいたいという人も多いですし。逆に、故郷を売りたくないんで貸す、という形ならばという人もいるし。そこは本当に国に柔軟に考えてほしいと思いますね。いろんな立場の人がいるんで」
安田「今、福島の問題の情報収集をしたいと思っても、震災に対して積極的に報道してきた新聞でさえ汚染水漏れがありましたぐらいで、テレビなんかですとほとんど目にしなくなりましたよね。木村さんが仰ったような声を聞きたいと思っても、なかなか自分たちの耳に入ってこないのが、今、東京にいての実感なんですね。何かしたいと漠然と思っていたとしても、漠然とした東北に対して私たちが頑張るって難しいと思うんです。たとえばそこに顔を知ってる誰かがいて、自分が出会ったことがある誰かがいるだけで、木村さんという人を知っている、木村さんが頑張っているから、大熊のことをもっと調べてみようとか、大熊のことについての情報発信を手伝えないかなとか。写真展とか、こういったトークライブをやる意味って、木村さんにみなさんが出会ってくださる意味があるのかなって思って。私自身、木村さんが住んでいた大熊という町をもっと知りたいと思ったので。なんて言うんでしょう、生で出会う、直接出会うということが、人を動かす何よりの原動力なのかなって思います」
渋谷「木村さんも私たちも、8階の写真展会場にいますので、直接話しかけていただけたら嬉しいです。『汐凪』の本もですね、少ない部数ですが、販売させていただきますんで。この本の売り上げは、震災遺児などの支援をしている団体に寄付されたりしているので、よかったら手に取っていだければと思います」

木村「自分も、この本に非常に救われたんです。木村汐凪の名前をね、ずっと残していきたいという思いで作ったんです。ひとつ例を挙げさせていただくと、あしなが育英会には、木村汐凪の名前で売り上げを寄付をしていて。お礼状の手紙が汐凪宛に来るんです。それも汐凪との繋がりで。そういう本なので、もしよかったら」
後藤「ぜひ、みなさん手に取っていただいて。8階のほうにみなさんいらっしゃいますんで、お話ししてみたいなと思う方もぜひ立ち寄っていただいて。そろそろお時間になってしまったのでこのあたりでと思うんですが、木村さん、今日は、どうもありがとうございました」