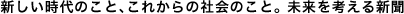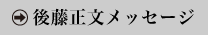後藤「みなさん、お集まりいただきましてありがとうございます。写真展はどうでしたか? 僕自身、展示を見て当時の気持ちをもう一度思い起こされて、うるっと来たんですけど…。今日は、この写真展の写真を撮り、『THE FUTURE TIMES(以下TFT)』にも二号続けて写真を掲載させていただいていますフォトジャーナリストの3人の方々と、短い時間ですが、トークができたらと思います。さっそくお呼びしたいと思います。フォトジャーナリストの佐藤さん、安田さん、渋谷さんです!」
佐藤「フォトジャーナリストの佐藤です。普段はアフリカなどで取材をしているんですが、のちほど話しますが故郷が東北にある縁で、震災以降、被災地での取材を重ねています。よろしくお願いします」
安田「みなさん、こんばんは。フォトジャーナリストの安田菜津紀と申します。普段はカンボジアなどの取材をしていますが、ご縁があって昨年から陸前高田を中心に東北の取材を続けています。よろしくお願いします」
渋谷「渋谷敦志と申します。私はアフリカ、最近ではソマリアなどの紛争地を取材しています。昨年からは佐藤君の故郷の陸前高田や釜石など岩手の被災地、そして福島も取材しています。どうぞよろしくお願いします」
後藤「それでは、お三方それぞれに3月11日、震災発生当時の状況を教えていただこうと思います」
佐藤「はい。実は僕たち3人は震災当日、ちょうど海外取材の最中で、誰も直接揺れを体験してないんですね。そのとき僕はアフリカのザンビア共和国にいて、インターネット経由で情報を得ました。でも東北沿岸地域の地震というのはそんなに珍しいものではなく、初めはそこまで大変な状況だとは思わずに心配してなかったんです。でも、岩手県沿岸の陸前高田市に住んでいる両親に電話をしても繋がらず、ネット上にも次々と甚大な被害の情報が入ってきて、すぐに緊急帰国を決めました。両親の安否もわからないまま、3月13日に日本に帰国しました」
後藤「当時は、どういう感覚でしたか?」
佐藤「全く現実感がなかったですね。一番初めに入ってきた陸前高田市の情報が『市街地確認できず』というものでした。画面上に表示される『壊滅』という文字。2万人ちょっとの人が住んでいる街が確認できないってどういうことだ、と恐怖を覚えました」
後藤「僕も当時の衝撃を憶えています。“壊滅”という言葉も聞いた気がするし。全く想像できなかったです。空撮の映像を数日後に見てようやく状況がわかって…。安田さんはどうでした?」
安田「私はフィリピンでインターネットも通じないような山奥にいました。日本の旅行代理店からかかってきた『日本で地震があったみたいですよ』という全く緊張感のない電話で地震のことを知りました。その後、徐々に情報が入ってきて、翌12日にフィリピンの新聞で『壊滅』という文字からその壊滅的な状況を知りました。その後、ようやく首都に戻って通信状況が整ったらツイッターのTLが『地震』の文字で埋め尽くされていて、これだけ通信技術が発達しても物理的な距離の差は歯がゆいものだと痛感しました」
後藤「なるほど。渋谷さんはどちらに?」
渋谷「私はウガンダでした。こういう話をしてると、どんな仕事をしている人たちなんだ?と思われそうですけど(笑)。そこで、フィリピンの安田から電話があって『佐藤の両親が行方不明だ』と。その後に、佐藤からツイッター経由で『帰ります』とメッセージが来ました。その頃に福島で原発が爆発している映像も見て、すごい動揺したりして。東京に着いたのが17日でしたね」

後藤「真っ先に東北の地に入ったのは、佐藤さんですよね?」
佐藤「そうですね。現地の父から『自分は無事だ』という電話があり、岩手の盛岡に父を迎えに行きました。ガソリン不足で手間取ったため、帰国の数日後、18日に東京を出発し、20日に再会しました。実際に津波被害を受けた沿岸地域に入ったのは22日です。その間ずっと渋谷さんとも連絡を取り合っていました。みな本当にパニック状態だったので、渋谷さんは『自転車でもなんでもいいから駆けつける』と言ってました。新幹線も止まってるし、車も持ってないから自転車で行く、と。『どうやって来るんですか?』と聞いたら…」
渋谷「新潟まで出て、秋田へ抜けて、盛岡までは新幹線が繋がっていた。そこから宮古経由で行けばいい、と。実際、東京で自転車で予行練習したら、家から武蔵小金井の駅に行くまでで『もう無理や』と…」
後藤「走行距離が短いですね、それ(笑)」
渋谷「15分くらい(笑)」
佐藤「3月に自転車で山越えするなんて、東北出身の僕からしたら無謀極まりないことでしたね。食べ物もあるかどうかもわかりませんし」
後藤「それで佐藤さんが先に現地へ入られてから…」
渋谷「僕が次に。会った時は佐藤が無事だったのでひとまず安心したのと、佐藤のお父さんが盛岡で入院してたんですがご無事で。ただお母さんが行方不明だったので、翌朝から探し始めて。その時はどこに何があるかわからないし、地理状況も把握できないし。僕は取材でしたけど、佐藤はお母さんを見つけることが先決だと思っていたので、そのことを彼に言いました」
後藤「そのとき、佐藤さんを見て渋谷さんはどう思いましたか」
渋谷「すごく疲れてるはずなのに執拗に瓦礫の写真を撮っている彼を見て、危うさを感じたんですね。なんだか消えてしまいそうな近寄りがたい空気があって、かける言葉も見つからずで。それで望遠レンズを使って彼を撮りました。彼がこの震災取材の最初の被写体でした」
後藤「こうやって佐藤さんと対面しても、――僕は先にあの写真に写っている佐藤さんを見たので、目が違うと思いました。あの写真だと、なんかこう意識が内側に入っているというか…」
佐藤「自分で思い返しても、自分ではない精神状態のようでした。瓦礫の街を歩きながら、ずっと母を探していました。被災者名簿の中に母と同姓同名の人を見つけては一人一人確かめに行き、結局みな違う。まるで、その人が助かったがゆえに母の死が色濃くなっていくかのような錯覚にとらわれました」

安田「そして私が一番最後に現地に入ったのですが、それまで東京で何ができるのか悶々としていました…。『フォトジャーナリストが被災地に行って何をするんだ』という声と、『フォトジャーナリストが現地に行かなくてどうするんだ』というふたつの意見の間で揺れていました。そんな時に、現地にいた佐藤から『とにかく被災範囲が広すぎる、情報を発信する人間が余りにも足りなすぎる』と言われ、最終的には現地からの声を信じて現地入りを決断しました。道路もあちこち寸断されていますし、陸前高田は市役所がかなりの被害に遭っていたので、『どこの避難所に何が足りない』という基本的な情報もほとんど手に入らない状況でした。自分にできることがあるかもしれない、と3月25日に現地に入りました」
後藤「その当時は、佐藤さんから見ても、現地での情報は錯綜していました?」
佐藤「そうですね、どこに何があるかわからない状況でした。東京の報道では『被災地でそんなことをしてはいけない、被災者にそんな言葉をかけてはならない、被災地はああだこうだ…』などと流れていましたが、ミクロとマクロの視点、両方必要なんですよね。実際には『被災地』という場所はないし、『被災者』という特定の個人はいないんです。僕の目の前に居るその人が何を必要としているのか、それを伝え続けるしかないのですが、とにかく人が足りない。こっちはなんでもあるのに、あっちはトイレットペーパーすらない。存在を知られていない避難所すらある」
後藤「どこに誰が避難しているのか把握されてない場所もあったんですね」
佐藤「そうですね。一般宅に3〜4家族で避難しているような場所は、特に」
安田「避難者の方々は行き来する余裕もない。こっちとあっちで情報交換すればいいのに、と思うでしょうが、そんな余裕がないんです。ならば動ける人が動いて伝達しよう、となりました」
渋谷「福島もそうでしたね」
後藤「渋谷さんはそのあと、南相馬から浪江に入られて」
渋谷「僕が福島に入ったのは、震災から3週間も経った時期だったんですけど。宮城、岩手と違って、ボランティアだけでなく、警察や消防隊員の姿も見なかった。ジャーナリストも少ない。忘れられてる、見捨てられている感覚というか…」
後藤「そのあたりは現地の方と話されて、どうでした?」
渋谷「そうですね、まず被災者の方から感じたのは怒りでしたね。あと、悔しさ。悔しさというのは、まず被災した方々は自分を責めるんですね。家族を助けてあげられなかった、見つけてあげられなかった悔しさ。そしてそういう状況にされた怒りをどこにぶつけていいかわからないから、国や東電に向けるんですけど、それでも上げた拳をどこに下ろせばいいのかわからない」
後藤「原発事故が震災の被害を複雑化させたわけですけれども、自分達の家族がいるであろう場所に入っていけない、探せないということ。人間としての尊厳を踏みにじられるというか、泣けてきますよね」
渋谷「僕は東京から行ったので、放射能のことが心配なわけですよね。でも現地の人たちはそんなこと気にしてられない、それどころじゃない。何十年先の後遺症より、まず家族を探す。そういう人たちは中に入ってたんです、入ってはいけないとされていた区域に。被曝の恐怖もあったでしょうが、人として当たり前の行動だと思います。それを知っていて行政は知らないふりをしていた。20km地点に警察がいるのですが、被災者の立ち入りを『気を付けてください』と言って大目に見ていた。誰が悪いというつもりはないですけど、そういう現実を伝えないといけない、と」


渋谷敦志(しぶや・あつし)
1975年、大阪府生まれ。高校生のときベトナム戦争の写真を見てフォトジャーナリストを志す。大学在学中にブラジルに渡り、法律事務所で研修しながら写真を本格的に撮り始める。London College of Printing(現ロンドン芸術大学)でフォトジャーナリズムを学ぶ。現在は東京を拠点に、世界の紛争や貧困、災害の現場で生きる人間の姿を写真で伝えている。1999年MSFフォトジャーナリスト賞、2000年日本写真家協会展金賞、2002年コニカミノルタフォトプレミオ、2005年視点賞・第30回記念特別賞など受賞。アジアプレス所属

佐藤慧(さとう・けい)
1982年岩手県生まれ。
studio AFTERMODE所属。大学時代は音楽を専攻。世界を旅する中でその不条理に気付く。2007年にアメリカのNGOに渡り研修を受け、その後南部アフリカ、中米などで地域開発の任務につく。2009年にはザンビア共和国にて学校建設のプロジェクトに携わる。
2010年studio AFTERMODEに入社、ジャーナリストとしてアフリカを中心に取材を始める。東日本大震災により両親の住んでいた街、陸前高田市が壊滅、復興支援団体「みんつな」を立ち上げ支援に関わりながら取材を続ける。写真と文章を駆使し、人間の可能性、命の価値を伝え続けている。2011年世界ピースアートコンクール入賞。東京都在住。

安田菜津紀(やすだ・なつき)
studio AFTERMODE 所属
フォトジャーナリスト
2003年8月、「国境なき子どもたち」の友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。2006年、写真と出会ったことを機に、カンボジアを中心に各地の取材を始める。現在、東南アジアの貧困問題や、中東の難民問題、アフリカのエイズ孤児などを中心に取材を進める。2009年、日本ドキュメンタリー写真ユースコンテストにて大賞受賞。共著に『アジア×カメラ 「正解」のない旅へ』(第三書館)など。上智大学卒。