90年代初頭にマイクロフォン・ペイジャー(※1)のメンバーとして日本のヒップホップに決定的な影響を与え、その後もDJ/ラッパー/プロデューサー/デザイナーとして活躍してきたMURO。承知の通り、彼は世界的にも有名なレコード・ディガーで、“KING OF DIGGIN`”の異名で知られている。かつては“世界一のレコードの街”と言われた渋谷だが、インターネットの普及とともに、オンライン・ストアに移行するレコード屋や閉店に追い込まれるお店が急増し、街の雰囲気も大きく変わった。そんな渋谷をホームに長年活動してきたMUROは今、何を思うのか? 彼が、2011年に渋谷ファイヤー通りにオープンしたセレクト・ショップ『DIGOT』で、レコードと音楽、今後の夢について聞いた
――今の時代にアナログでDJすることをどう捉えていますか?

MURO「やっぱりDJの入りがレコードだから、DJをするときに使うレコードは、野球をするときに使うバットやグローブのような道具と同じ感覚なんです。ジャケットからレコードを出して、ターンテーブルに乗せて、針を置いて、曲の頭出しをする。テクノロジーがどれだけ進化しようとも、何十年とやってきた、その一連の動作が体に染み付いているんです。DJは職人みたいなものですから。レコードを毎日買ったり、聴いたり、DJで使ったりするのは、ご飯を食べるのと同じように自然なことなんです。7インチとかDJ始めたころから見過ぎちゃってるし、パソコンの液晶画面で選曲するのは、なんか難しいなあって」
――身体感覚みたいなものですね。
MURO「そうですね。ニューヨークとか海外に行って、自分が好きなDJとやらせてもらったりするときに、もちろんやってるフリじゃないですけど、パソコンでDJするのを見ちゃったりすると、ちょっとね(笑)。なんか悲しいなあっていうか。ライブ感もないし、やっぱりDJは音だけじゃないんだなあっていうのはありますよね」
――DJがブースのなかでレコードと格闘しながらせわしなく動いている、あのアクションもDJプレイの醍醐味ですよね。
MURO「うん、そうですね」
――音楽はどんどんデータ化が進んでいるじゃないですか。例えば、代表的なものにMP3がありますよね。石野卓球さんが音楽ウェブ・サイト『ele-king』のインタビューで、「あれ(MP3)は個人で聴くものでみんなで聴くものじゃない。レコードはひとりで所有するものっていうよりもみんなで聴くものっていう俺の概念があってさ(笑)」って語っていて、すごく腑に落ちたことがありました。
MURO「ああ、なるほど。それは素晴らしい考えだと思いますよ。僕は今もアナログを毎日買っていて」
――毎日はやっぱり凄いですよね(笑)。
MURO「はい。それと、とくに震災以降、アナログをいかに活かすかということを考えるようになって。そんなときにレゲエの現場も増えてきて、レゲエとサウンドシステム(※2)文化のアナログの活かし方に感動してしまって(笑)。サウンドシステムの歴史を遡っていろいろ調べていったら、なんで今まで気づかなかったんだろうってことがたくさんあって。今のクラブは、セラート・スクラッチ・ライブ(※3)に合わせた音響設備が主流になっていて、重いレコードをどんだけ大変な思いをして持って行っても、気持ち良くプレイできる現場が減ってしまって。かつてだったら、たとえばディミトリ(※4)が『YELLOW(※5)』に来るときに、“ディスコのセットでDJして欲しい”って依頼が来ると、膨大なレコードを収納した棚の前に立って“何をかけようかな”とあれこれ考えながら選曲していて、それが楽しくてしょうがなかった。そういう興奮を味わう機会が少なくなったのは悲しいですね。ただその一方で、海外でロックの新人アーティストが7インチで新曲を切るみたいな文化がここ何年か流行り出していて、アナログを見直して掘る人たちが少しずつ増えているんです。だから、いまは海外に行くときがいちばん楽しいですね。ニューヨークでもそういう流れがあって、『ParkJam(※6)』という野外パーティに呼ばれてDJしたりもしてます」
――それはブロック・パーティ(※7)みたいなものですか?
MURO「そうですね。僕はやっぱりニューヨークのブロック・パーティから出てきた音楽に影響を受けて来たのもありますし、そこで回したいって夢がずっとあって。一昨年ぐらいに初めてDJすることがあって、それ以来毎年回させてもらってるんです。ハーレムの公園でやるんですけど、圧倒的に家族連れが多いですね。こっちでいう盆踊りみたいな感じで、お父さんが息子に、“とうちゃんは昔、この曲で踊ってたんだぞ”みたいなことを熱く語っているんですよ(笑)。そういうのがすごいいいなあって」
――選曲もソウルとかファンクとかラテンからヒップホップまで、幅広い感じですか?
MURO「そうです。もう幅広くて。パイオニアの人たちもDJやるんですよ。グランドマスター・フラッシュ(※8)とかキッド・カプリ(※9)とか。で、グランドマスター・フラッシュも今回はレコードでやるとか、そういう動きがあるんです」
――なるほど。
MURO「3年ぐらい前に東洋化成の方と会う機会があって。アジアで唯一のレコード・プレス・メーカーですね。で、それこそレコード・ストア・デイのことを話しに行ったんですよね。“日本でも何かやらないんですか?”って。たとえば代々木公園で、海外からレコード・ディーラーを呼んで新しい形のレコード・コンベンション(※10)をやるとか。日本だとやっぱり後楽園ホールでやるレコード祭りとかになるんで」
――ちょっとマニアックになっちゃうんですかね?
MURO「そうなんですよ。若い人が行きづらいんですよ。現場として、僕も圧倒的に海外のレコード・コンベンションの影響を受けてきたんです。ルーズベルト・ホテル(※11)のラウンジを借りて、近郊から集まってきたディーラーさんが家族といっしょにテーブルを出して、子供がレコードをテーブルに載せるのを手伝ったりとか。そういうところに買い付け行くと、日本人とかもそのころは多かったですね。早く入るためにちょっとお金を払って入ったりするシステムがあったり。93年に初めてニューヨークに行ったんで、それ以降はけっこう頻繁に行ったりしてましたね」

――さきほど、震災以降、アナログの音をいかに活かすか考えるようになったと話されていましたけど、それはどのような変化だったんですか?
MURO「やっぱりこう、これだけ変化があると、考えも変わってきますよね。もちろん、制作が煮詰まっているときにレコード屋さんに行って店員さんと話したり、レコードを聴いたりしてヒントを得たりするのはいまも昔も変わらないですし、デザインで困っているときにレコードのジャケットを眺めているとインスピレーションが湧いてきたりもしますよ。ただ、あの地震で、天井まで積み上げてたレコードが初めて全部倒れちゃったんですよ。3階の部屋で。割れたりするレコードはなかったんですけど、自分がいちばんシャカリキになって買い集めていた90年代のラップのレコードたちが、ソウルやファンクのレコードたちをかばうかのように倒れたりしてて……。ちょっとホロッとしてしまって」
――震災はモノの儚さを痛感させられる出来事でもありましたよね。
MURO「そうだと思いますよ。トライブ(ア・トライブ・コールド・クエスト)(※12)のQ・ティップは相当なレコード・コレクションを火事で燃やしちゃってるじゃないですか。火事のあと、僕がニューヨークに買い付けに行ってるときに、Q・ティップが1ドルのレコードが詰まった箱を掘ってるところに遭遇したことがあるんですよ。それまでは絶対壁レコ(レア盤)しか買わないような人だったんですよ。コンベンションでも、ディーラーと知り合いだから、裏に行ってヘッドホンで聴けるような待遇のスーパー・プロデューサーですよ。そんな彼が1ドル箱を掘ってるのを見たときに、さすがだなって思いました。すべてが燃えたあとに、それでもレコードを掘る姿勢が変わらないっていう。去年ぐらいかな、お会いしたときに、“何探してるの?”って聞いたら、すごくレアなレコードを探してて。そこまで到達してんだなって。取り憑かれちゃうんじゃないですかね、やっぱりいろいろ」
――MUROさんは最近どのあたりのレコードを掘っているんですか?
MURO「やっぱり掘れば掘るほど南に行くんですよね。ようやくアフリカに辿り着きました。実際アフリカにもワールドカップのときに行かせてもらって。いまアフリカ音楽の再発が毎月のように出てて、それがすごいいい感じなんですよ。ああ、こんなのもあったんだって」
――昨年はイスラエルに行かれたそうですね。
MURO「そうなんですよ(笑)。そういうところに行って、レコードがあったり、DJがいたりして、いろんな人と触れ合ったりすると、いままでずっとアメリカしか見ていなかったから、おもしろくてしょうがないんですよね。タイとかトルコとかの音楽も気になるし、ベリーダンスの教訓用のレコードみたいのも売ってるんですけど、そういうレコードのなかからファンキーなものを探してますね」
――『ファインダーズ・キーパーズ(※13)』がトルコや東欧のサイケデリックでファンキーな盤の再発に力を入れたりしていましたよね。
MURO「そうそうそう。ちょうど今度マッドリブ(※14)とイーゴン(※15)が日本に来るので、トルコとかのファンクを教えてもらおうかなと思ってますね」
――探求の旅が止まらないんですね。
MURO「そうなんですよ(笑)。それと今は、いろいろ逆転していておもしろいんです。昔は“これが日本のブレイクビーツだから”って日本の音楽を外国の人に教えても、“あ、そうなの?”って鼻で笑われるぐらいだったけど、今じゃ情報でもなんでも“ください、ください”って感じで。90年代はカセットテープが20本ぐらい入る、ジュースを入れるようなクールバッグを腰に二つ付けてレコードの買い付けに行って、ニューヨークでアーティストとかレコード屋さんに“聴いてみてくれ”って撒いて歩いても、当時はもらってもらうのがやっとだった。いまでは“くれ、くれ”って言われるようになって。日本の音楽の歴史に気づいちゃったんですよ」
――なるほど。アナログの、人を虜にする魅力を若い世代にも伝えて行きたいという思いをMUROさんは強く持たれているんですよね。
MURO「それはありますね。地方営業とか行かせてもらうと、僕の出るパーティはほぼ全員アナログですね。東京だと逆に信じられない光景になってますよ。東京にも『IN BUSINESS(※16)』とか生音のパーティがありましたけど、1回クローズになっちゃって。でも、また今年から始まりますし、そういうコアなパーティは増えそうですけどね。『UNDER DEER LOUNGE(※17)』ってこのお店の隣りの地下にライブ・ハウスがあって、そこでドーナツ盤だったらどんなジャンルでも回してくださいっていうフリーイベントを始めたんですよ。1回目を昨年11月にやったんですけど、ビールが売り切れたんですよ! それで嬉しくなっちゃって、2回目以降も続けていこう、と。ジャンルも型も世代も関係なくやっていけたらなと。そういう現場作りはしていきたいですし、自分が出す作品はできるだけアナログで切っていきたいなと思いますね」
――ドーナツ盤の魅力はどこにありますか?
MURO「7インチ・レコード、ドーナツ盤でDJしていると、知らない人が見てもやっぱりおもしろいと思うんですよ。こんな小っちゃいレコードをDJで回してるなんて(笑)。1人でもおもしろがってくれればいいなあって気持ちでDJしてます。だって、元々ジュークボックス用に作られたレコードを2枚使って、ブレイク・パート(※18)をループしたりするって狂ってると思うんですよ(笑)。それで踊らせたり、その上にラップを乗っけたり。自分もそういうDJを続けてたら、最近になってテクニカルな若い子がどんどん出てきて、頼もしい現場が増えてきましたね。逆に自分は好きな音楽だけを発信すればいいっていう気持ちでやっていて、いい環境になってきてますね」
――これだけ無料で、労力をかけずに音楽を聴ける時代だからこそのアナログ再評価であり、モノの価値を見直そうという動きなのかもしれませんね。
MURO「それは感じていますね。ここ数年、各ジャンルでレコード・アイテムとしてそそられるアイテムがすごく多いですよね。僕はアイテムとしてのレコードに愛着がありますから。それこそジェイムズ・ブラウンのライブ・バージョンの7インチとかリー・ペリーの10インチのボックス・セットとか。ほんと素晴らしいパッケージもあってやられますよ」
――今後の野望というか、夢はありますか?
MURO「さっき言ったみたいに大きいコンベンションだとかパーティだとかDJイベントとか野外でやったりしたら、町おこしできると思うんですけどね(笑)。一昨年、このお店の前の通りを少し下ってすぐのところにあるディクショナリー倶楽部(※19)さんの庭で、『Do Over(※20)』っていうLAのパーティの東京版をやったんです。DJも誰が来てどんなレコードを回すのかその日までわからないっていうのを売りにしているパーティで、すごく楽しかった。昼間から、それこそ家族連れの人もたくさんいましたね。僕が『HARLEM(※21)』でDJしているときに遊びに来ていた女の子がお母さんになって子供といっしょに来たりしてて(笑)」
――世代を越えて、MUROさんのDJが浸透し始めているんですね。さっきのMP3の話じゃないですけど、音楽が1人で聴くだけものになっていってしまったら、それは淋しいですしね。

MURO「地方のトップ40がかかっている大箱とかに勉強のためにたまに行ったりするんですよ。どれぐらいの人が入っているのかなど、知りたくて。で、たまに“DJがいらないんじゃないかな?”と考えさせられちゃうときもあって。クラブは日本ではどんどん印象が悪くなっていっているし、踊る現場がないとそもそもダンス・ミュージックの役割もない。でも、だからこそ、自分で発信して、場所を作るためにオーガナイズする人も増えてくるんじゃないかなって。レゲエの現場もそうですけど、野外で昼間やるパーティはやっぱりすごい気持ちいいなあって思いますし、自分のサウンドシステムとレコードで音を出せたら、これほど贅沢なことはないなって(笑)」
――それこそ『ParkJam』みたいな野外パーティが根づく土壌は日本にも十分にありますよね。
MURO「実際あると思いますし、いまの若い子たちは変にアメリカナイズされてなくて、発信する音楽も幅広いし、日本の昔の音楽もかけられるわけだし、そしたら親子の会話にもなりますよ。だから、すごくおもしろいことになるんじゃないかなと思うんですけどね」
――ここ数年で他に印象に残っているパーティやイベントはありますか。
MURO「去年『南祭-2012NANSAI-』っていう大阪のミナミの古着屋さんや美容師さんが毎年やってるイベントに呼ばれたんです。夕方ぐらいから始まって、和太鼓のグループとかバンドとか、いろんなジャンルの人たちが出る、町の活性化イベントなんですよ。三角公園の裏にあるクラブでやったんですけど、すごかったですよ。50年代、60年代の音楽を7インチでかける人とかいろんな人がいましたね。ああいうイベントがまた増えてくるのかなとか」
――今日の話を聞いていて、MUROさんは世代を越えて、家族でも楽しめるようなパーティを広めていきたいという夢があるのかなと思いました。

MURO「やっぱり入りがそうだったからでしょうね。レコード屋でブラック・コンテンポラリーとヒップホップのレコードがジャンル分けされていない80年代から、いかにヒップホップを広げて行くかということを考えてましたから。当時は日本盤のレコードも全然少なかったし、貸しレコード屋さんがメインでしたね。ローラースケート場とかでチェックして貸しレコード屋さんに毎日借りに行ってましたね。いまやローラースケート場も貸しレコード屋さんもないですもんね(笑)」
――あ、でも、去年、T.R.E.A.Mってクルーがヒップホップとダンス・ミュージックのパーティをローラースケート場でやってましたよ。だいぶ盛り上がったみたいで。
MURO「いいなあ、ローラースケート場。天然な感じが」
――クラブももちろん楽しいですけど、野外とか、不特定多数がいる町中で音楽が響くってやっぱり特別な興奮がありますよね。
MURO「そうなんですよね。だから、『Do Over』をやって以降、ここ(『DIGOT』前のファイヤー通り)を歩行者天国にしてパーティする目標ができましたね。自前のサウンドシステム出して、パーティして、通りおこしをやりたいですね(笑)」

MURO 『J.a.M』
去年リリースした『DIGGIN’FOR BEATS』からの限定先行7インチです。ここ数年掘りはじめた世界のいろんな国のレコードからサンプリングしたブレイクビーツです。この曲ではあるインド映画の一部分を使っています。今後の新たな展開に向けたガッツの一曲ですね。

DINKY-DI 『HARLEM RIVER DRIVE』
日本のユニット『Dinky-Di(ディンキー・ディー)』が70’sの名盤『Black&Blues』をリアレンジ、2004年にリリースされたものです。最近は、クオリティの高い作品やカバーを提供してくれる日本のアーティストがすごく増えてきたので、これからがとても楽しみです。
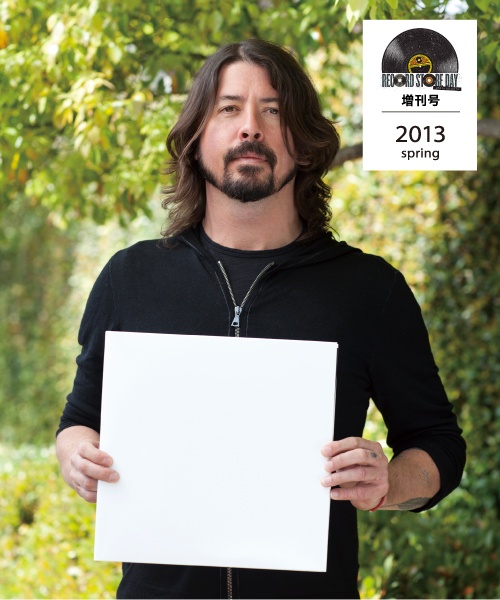

MURO(むろ)
埼玉生まれ。DJ/ラッパー/プロデューサー/デザイナー。“KING OF DIGGIN’”の異名を持ち、レコード・コレクターとしても世界的に高く評価されている。ヒップホップ・グループ、『マイクロフォン・ペイジャー』のメンバーであり、デビュー・アルバム 『DON'T TURN OFF YOUR LIGHT』(1995年)は、その後の日本のヒップホップに決定的な影響を与える。『PAN RHYTHM:Flight No.11154』をはじめ、ソロ・アルバム多数。2011年、渋谷ファイヤー通りにセレクトショップ『DIGOT』をオープン。
■注釈
(※1)マイクロフォン・ペイジャー
MUROやTWIGYらメンバーで1992年に結成された、日本のヒップホップグループ。日本語ラップというジャンルの確立に大きく影響、また貢献した重要なユニットである。
(※2)サウンドシステム
レゲエに端を発する野外でパーティをするための移動式音響設備や、それを提供する集団のこと。移動式の巨大スピーカーセット、アンプ、ターンテーブルそしてレコードのことを指す。
(※3)セラート・スクラッチ・ライブ
パソコンにあるmp3等の音楽ファイルを、アナログレコードのようにスクラッチなどもしながらプレイできるソフト。現在のクラブではこのシステムが導入されているところが非常に多くなってきている。
(※4)ディミトリ
ディミトリ・フロム・パリは、フランス出身の作曲家でありDJ。パリでハウスと呼ばれるダンス・ミュージックの人気を確立させたことで有名。世界的に有名なファッションブランドのショーで音楽演出なども手掛けている。
(※5)YELLOW
1991年にオープン、2008年のクローズまで17年間にわたり東京・西麻布で音楽シーンを作り続けたクラブ『Space Lab YELLOW』のこと。国内外の大物アーティストがライブやDJプレイを披露し、世界のトップクリエイターたちが繋がる伝説の場だったといわれる。
(※6)ParkJam
ニューヨークで夏季に週1回、ブロンクスやハーレムといったエリアの公園で開催されているオールド・スクール・ヒップホップのイベント。そうそうたる出演者が名を連ねているにも関わらず無料で誰でも楽しめるイベントであり、親子連れにも人気が高い。
(※7)ブロック・パーティ
70年代にアメリカで生まれた、地域単位で行われるダンスや音楽を中心としたパーティで、エリアの住民が一体となって盛り上がる宴とされる。主に野外で行われることが多く、サウンドシステムの電源は街灯などから非合法で取られることも多いが、警察などもそれを大目に見るケースがほとんどだという。
(※8)グランドマスター・フラッシュ
1958年生まれ、アメリカを拠点に活動するヒップホップ・ミュージシャン。70年代にニューヨークのブロンクスで開かれていたブロック・パーティを原点に持つ彼はヒップホップの開祖ともいわれる。レコードを逆回転させ演奏した初めてのアーティスト。
(※9)キッド・カプリ
1970年生まれ、ニューヨークはブロンクス出身のDJ。幼い頃より人前でDJプレイを披露していたというほどの伝説の存在であり、“ミックステープの父”とも言われる。ヒップホップというジャンルが確立する前から活躍してきた。
(※10)レコード・コンベンション
レコードディーラーが多数出店する展示会・レコードの掘り出し市のようなもの。ニューヨークで行われているWFMU RECORD FAIRはニュージャージーのインディペンデントラジオ局が行っており、アメリカ最大のレコード・コンベンションとされる。
(※11)ルーズベルト・ホテル
ニューヨーク、マンハッタン中心部で1924年から営業するクラシックなホテル。セオドア・ルーズベルト大統領にちなんだ名前を持ち、バンケットルームや会議室なども多く人々の交流の拠点にもなっている。
(※12)トライブ(ア・トライブ・コールド・クエスト
1988年結成、アメリカのヒップホップグループ。1998年に一度解散したが、2006年再結成。伝説的グループである彼らのドキュメンタリー映画『ビーツ、ライムズ・アンド・ライフ~ア・トライブ・コールド・クエストの旅~』が2012年に日本でも公開となり話題に。
(※13)ファインダーズ・キーパーズ
ワールド・ミュージックや民族音楽を中心として発掘、リリースをしている音楽レーベル。主宰者はアンディ・ヴォーテル。
(※14)マッドリブ
1973年生まれ、アメリカのミュージシャン/音楽プロデューサー。アンダーグラウンド・ヒップホップと呼ばれるシーンで活躍している。
(※15)イーゴン
アメリカ西海岸のアンダーグラウンド・ヒップホップ・レーベル『STONES THROW』を運営する立役者。レコード・コレクターとしても有名。
(※16)IN BUSINESS
2006年に東京・渋谷のクラブエイジアにてスタートしたDJとバンドが混在する形で繰り広げられるパーティ。これまでに30回以上の開催実績を誇る。現在は代官山UNITにて開催されている。
(※17)UNDER DEER LOUNGE
東京・渋谷のファイヤー通り沿いにあるパーティ・スペース。MURO氏のお店に隣接している。
(※18)ブレイク・パート
ファンクの曲などで、曲の間奏部分で入るドラム・ソロ部分のこと。
(※19)ディクショナリー倶楽部
編集者/放送作家/選曲家などさまざまな顔を持つ桑原茂一氏が主宰する『クラブキング』が運営するアート・カルチャースペース。イベントなども多数開催される。2013年春に、東京・神南から千駄ヶ谷へと移転。
(※20)Do Over
ロサンゼルスで開催されているブロック・パーティ。毎回豪華なシークレット・ゲストが登場することでも有名。
(※21)HARLEM
1997年に東京・渋谷にオープンしたクラブ。日本におけるブラック・ミュージック、ヒップホップの聖地。http://www.harlem.co.jp/







