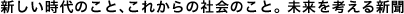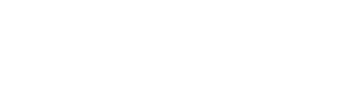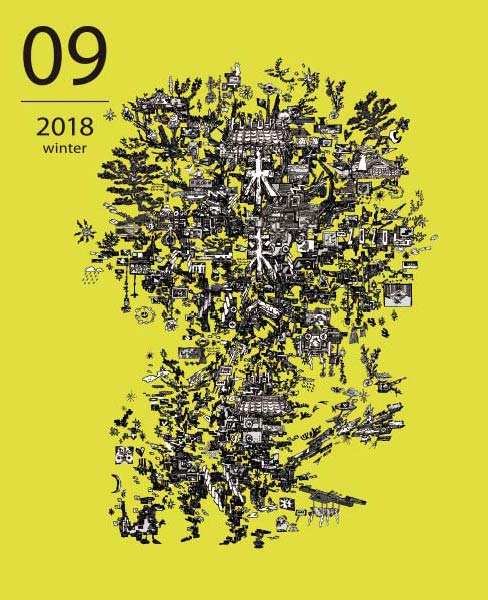温 「今の世の中ってSNSがすごく発達していて、誰でも自分の言葉を発信できる状況ではあるんだけれども、そのせいで、言葉を奪われている人がすごい多い気がして、危惧してるんです。たとえば、ネットで誰かや何かを批判してる人たちの言葉遣いって、どれも似たり寄ったりなんですよね。罵られてる対象がひどく傷つけられているのは言うまでもなく、罵ってる側もまたネット仕様に簡略化されてゆき、そのせいで蝕まれているというか……」
後藤 「なるほど、感情のテンプレートというか、スタンプみたいな感じですよね」
温 「そうそう、そうなんです。自前の言葉を模索せずに、絵文字、スタンプといったあらかじめ用意されたテンプレートでイージーに自分を示しちゃう。だから他人との関係も雑にならざるを得ないし、怖いのは、テンプレートからこぼれ落ちているはずの自分自身の感情の細やかな部分も無意識に切り捨てているんですよ。そういう状況を見ていると切なくて」
後藤 「それって〝言語って誰のものなんだろう〟っていう問題にも繋がると思うんです。ほんとは使う人のためにあるはずなんだけど……」
温 「まさにそう。言葉と個人の関係って、もっと繊細なはずなんです。そんな簡単に絵文字やスタンプに置き換えられるものではない。それで思い出したのだけど、以前、博多に行ったときに、ある年配の女性と話していたら、そのイントネーションというか口調が、台湾の祖母とどことなく似ていて懐かしくなったことがあるんです」
後藤 「へぇ」
温 「実は、日本統治時代の台湾に日本語を教えに行った日本人って、九州出身の方がすごく多いそうなんですよ。それで、博多でそのおばあさんと話しながら、私の祖母の国語の先生は福岡出身だったのかもしれないな、と考えました。日本と台湾の歴史を考えたときに、かつての日本が台湾人に日本語を学ばせたというのは本や資料を読めばいくらでも書いてあるけれど、そこにどんな感情の流れがあったのかまではわからない。私は博多でその方と話しながら、少女の頃の祖母がこういう話し方をする先生に耳を傾ける姿をはじめて想像して、言葉というものは抽象的なものではなく、もっとこう個人の人生経験そのものを反映しているものなんだなあ、と改めて痛感したんです。だから私は、言葉ってやっぱり個人と個人が触れ合うためにあると思うんです。日本人として、とか、台湾人として、とかではなく」
後藤 「確かに言語って、とことんローカルな領域まで切り分けていけば、その人自身、つまり個人の領域まで分解できるはずなんですよね。だけど、みんな大きなまとまりが大好きだから、とりあえずどこかに帰属したがる」
温 「そう。安全ですしね。その中にいれば晒されずに済むし」
後藤 「そこが難しい。温さんのおっしゃるような次元まで分解していったら、たぶん他者に対する思いやりとか、もう少し敏感になって、結果的に良い方向に向かっていくんじゃないかなっていう感じはする。ところがSNSのように簡単に語ることができる場所が増えると、一方ではスタンプみたいな表現ばかりが使い回されてどんどん言葉がひとかたまりになっていっちゃう」
温 「結果的に個人として発言することの難しさが増していくなっていうのを感じます。私に限っていえば、自分はこう思う、と言ったときに、発言そのものが吟味される以前の段階で、発言者は外国人だから、といった見方をされて、そこを批判されちゃうキツさがある」
後藤 「向こうから勝手にやってきますもんね、カテゴライズ」
温 「自分のコントロールの利かないところで、型に嵌められてしまう。最近は、そこを逆にはぐらかしたいなって。たとえば、〝外国人を差別するな〟とか〝多文化共生社会を目指そう〟とストレートに訴えるのは、言葉の使い方としてはある意味、簡単です。でも、こういう正しすぎる言葉に寄りかかっていると、初めはパワーがあったはずの言葉本来の輝きがどんどん鈍る。言葉に自分の実感が伴わなくなってくると、結局、自分を型に嵌めてくる人たちと同じなんじゃないかなって。だから、なんとか私個人が理想とする居心地良さみたいなものを、自分の言葉で積み重ね続ける方法はないだろうかって考えていて」
後藤 「それおもしろい。自分が居心地良くいることが、何よりもそういう居心地悪さに対して抗うってことですもんね」
温 「はい。でも一方で、そういう居心地悪さに自分で気がついていない方もまだたくさんいて。そこから引きずり出したら怒られるんだろうかって考えちゃうこともある(笑)。目覚めさせちゃったらどうしようみたいな」
後藤 「なるほど。でも、それは引き裂かれていいと思いますね。ものを書く人の責任というか。誰かが書いてしまったばっかりに、〝私、居心地悪いチームに入っちゃった〟って感じる人もいるかもしれない。でも、誰かがそれを言わなかったら、それ自体がなかったことにされてしまう可能性もあるから」
後藤 「僕も最近、〝魂の解放運動〟っていうのを勝手にやってるんです。とにかくみんな、それぞれに自由に楽しんでもらいたい。たとえば、日本のオーディエンスってコンサート会場でみんな同じように手を振るんですよ。でもそれについて僕が〝マスゲームみたいで不自由そうに見える〟って言うと、むしろ怒る人もいるんですよね。〝私は好きでこうやってるんだ、自由にやってるんだ〟って」
温 「確かに、そういう人もいるでしょうね」
後藤 「その一方で、海外のコンサート会場とかを回って比べてみると、やっぱり日本はなんらかの抑圧によって、みんながそうしてしまう状況ができてるんじゃないかとも思う。だから、もう少し大きい視点から解きほぐしたいって思うんだけど、言葉にして指摘するのがめちゃくちゃ難しくて。僕なりに考えた結果、誰よりもまず僕自身が自由に踊ってみせるっていうのをやろうと思って。最近はステージ上でも、感動したらとにかく変でもいいからちゃんと大げさに踊って、楽しくパフォーマンスしようって決めてるんです」
温 「それはすばらしいですね。とりあえず、深く感じ入った自分をまるごと晒してみる」
後藤 「温さんがご自身やご家族について書くのと同じですよね。やっぱりみんな人目を気にしてるんですよね。人のことも気にしてるし」

温 「そうそうそう。ちょっと人からヘンと思われたら、それでジ・エンドみたいな風潮には抗いたいですよね」
後藤 「ユニークっていいことなんじゃないのって僕は思うんですけどね」
温 「まさにまさに。ユニークはとっても素敵なんです。でも日本だとたぶん学校に通ってるうちに、先ほどおっしゃっていたように、ありもしない〝普通〟を学ばされちゃう。だからこそ、ほんの一歩、別の文化圏に踏み出すだけでも、それまでの自分を縛っていた〝普通〟から解放されて楽になる人って多いんじゃないかなってすごく思うんですよね」
後藤 「エッセイの後半あたりからずっとドキドキしながら読みましたもん。思考がアジア全体に広がっていくようなものを書いてみたいっておっしゃってましたよね。あれは是非やってほしいと思いました。 それこそASIAN KUNG-FU GENERATIONっていうバンド名もそういう発想からスタートしてるんですよ。僕らなんか、たぶん外国に行ったら単に黄色人種として扱われるんだろうなって思って。だったらそれを逆手にとってアピールしてやろうって考えたんです」
温 「日本の中だけにいると、たとえば私の場合は〝日本人じゃない〟っていう部分が誇大化してくるんだけど、ちょっと違う場所に身を置けば、単に〝日本で育った東アジアの植民地の子孫のひとり〟っていうふうに視野がまるっきり変わってくる。同じ自分のはずなのに。そういう、自分のことを肯定し直せるきっかけって実はいくらでもあるんだっていうことを伝えていけたらいいなと思っています」