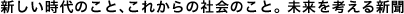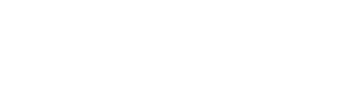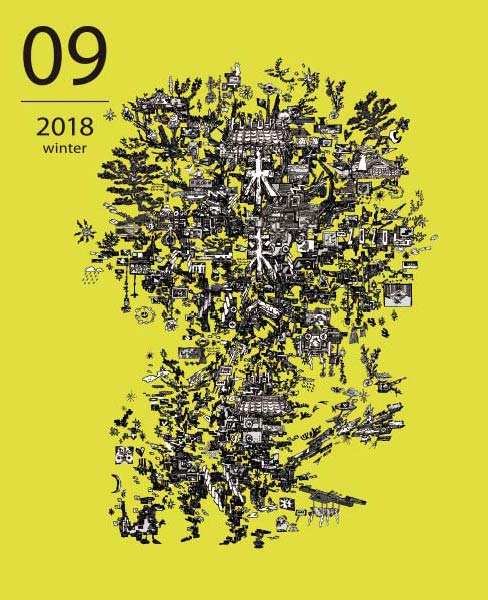東日本大震災以前から、代替エネルギーの推進に積極的に取り組んできた静岡県で今、新たな発電事業が注目を集めている。
近隣から収集してきたゴミをバイオマスの力で電気に変え、エネルギーの“地産地消”に繋げることを目標にしているという「牧之原バイオガス発電所」の挑戦を現地で取材した――。

日本有数のお茶の生産地として知られる、静岡県牧之原市。取材へ向かう車の窓の外を、広大な茶畑、そして食品製造工場の建物が次々に流れていく―。
2017年3月に運転開始した「牧之原バイオガス発電所」は、周辺地域で収集された「ゴミ」を原料にして発電を行っている。1日あたりの発電量は約15,600キロワット。それを中部電力に100%売電している。発電所を運営するアーキアエナジー株式会社の大橋徳久(おおはし のりひさ)さんは言う。
「今のところ、近隣の約1600世帯分の電気使用量をまかなっている計算になりますね。バイオガスの利点は何より、人の手で原料を投入しさえすれば、24時間発電し続けられるところです」
主な原料となるのは、食品クズや残渣(ざんさ)をはじめとした食品廃棄物。発酵させることで可燃性のメタンガスが生成され、それが発電の燃料になる。有機性のものであれば、ほぼなんでも原料になるという。牧之原市周辺は首都圏からのアクセスが良く流通に適しているため、広大な敷地を持った大手の食品製造工場が多く立ち並ぶ。ここから毎日大量に出る「ゴミ」が、バイオガス発電所があることで一転、「資源」に変わるのだ。
発電所に運び込まれる食品廃棄物は1日80トンにも及ぶ。各工場からトラックで回収されてくると、敷地内に並べられた鉄製のコンテナに一旦、溜め置かれる。大橋さんに促されてコンテナをのぞき込むと、レタスやジャガイモといった野菜クズ、コンビニ弁当の惣菜と思しき卵焼きの断片、チョコレートやクッキーの崩れた欠片(かけら)などが、山のように盛られている。少し生臭いにおいが漂っているコンテナもあったが、イメージしていたような強烈な腐敗臭はない。
しかし、なかにはつい数日前まで店頭に並んでいたであろう、パッケージが未開封のままの廃棄物も見られた。賞味期限前のものまであり、少し複雑な気持ちになる。
「未開封のものは、検査で規格を満たしていないと判断された商品だったり、製造の過程で異物が混入してしまった可能性のある商品だったりすると思うんですが、確かにもったいないですよね……」
原料のうち、容器に入っていたものは「前処理棟」で破砕分離を行う。また、液状の廃棄物と固形の廃棄物のバランスをみながら水分を調整し、メタン菌の餌となる酸生成を行う。その後、原料は発酵タンク内で20日くらいかけて分解され、バイオガスを生成する。
発酵前処理からガスの生成にいたる一連のプロセスは、「人間の体内の構造や働きになぞらえて考えることができる」と大橋さんは言う。

「前処理棟(まえしょりとう)で行う破砕(はさい)処理や水分調整は、人間が口の中で食べ物を咀嚼(そしゃく)したり、唾液で消化しやすい状態にするのと似ています。また、タンクの内部は24時間、バイオガスの発酵に適した温度に調整されているのですが、これが36〜40度くらい。実は人間の胃や腸の活動に適した温度も36〜37度と言われているんです。また、発酵によって生じるバイオガスは、人間が腸内で栄養吸収をする過程で生じるオナラのようなものでしょうか」
生成されたバイオガスはすぐに施設内の発電施設へ送られ、バイオガス専焼発電機で効率よく発電。その後、中部電力へ売電されるサイクルになっている。