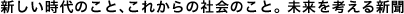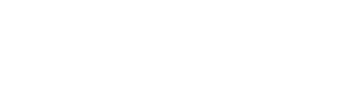その人が何を考えて、
普段どう暮らしているのかが音楽に出る
後藤「やっぱり身体性みたいなものを問うてるわけよね」
永井「はい」
後藤「私が私であるみたいな、実存みたいな、それがどんどん危うくなっている。私たちの音楽はどこにあるのかしらみたいな。無数のコピーがただちに飛んでいって、俺たちがいてもいないくてもいいみたいな。そういうメタバースのなかというか、インターネットのなかに放り込まれていくわけだよね。でも、私たちは、このユニバースを生きている」
東郷「この(身体の)内側さえ見たことないし、名前も知らないけど、ずっとやってくれてるわけじゃないですか、朗らかも、ここで」
後藤「でも、本当に布地に触れてよかったって思わない? 着せ替えのアバターの服とかさ、ときどき作ってみようかしらみたいな感じで、iPhoneとかでアバターを作ってるときにさ、ある程度のところで虚しさが込み上げてくるもんね、何をしてるんだろうみたいな。なんでこんな、どの髭が俺っぽいのかなって考えてるのかなって(笑)。随分巻き取られてるなって思うじゃん」
永井「あはははは(笑)」
後藤「でも布地に感触があることはすごいことだし、縫製が甘いよねみたいなことも含めて、人の仕事の積み重ねがあるけど、それを想像できて、手で触れられるかって、すごく大事な気がするっていうか」
永井「あー、なるほど」
後藤「音楽って基本的には触れないからさ、清丸がさっき鳴らしたギターの音とか、こうやって手で捕まえて、丸っと持って帰って誰かに聞かせてやろうとかできないから」
永井「できないですね」

後藤「そういう意味では、我々は身体性みたいなものに敏感なんじゃないかな。あと、やっぱり楽器の演奏ってめちゃくちゃ身体的なことだし、打ち込んだ音ひとつとっても、その人が何を考えて、どんな本を読んでて、どんなものが好きかってことが出ると思っていて。このボディが普段どう暮らしているのかが、めちゃくちゃ音楽って出る。だから、自分がやることを測量したくなる気持ちがすごいわかる。関わってる人は自分のボディじゃないけど、その人には私の何かが届いていて、アジカンだったら、チームアジカンはひとつのボディとして活動するわけじゃない?」
永井「はいはい」
後藤「そういう意味の身体性もあるし、チームの身体性というか」
東郷「アジカンを生で観たとき、巨大ロボみたいって思いましたもん。チームとしてね」
後藤「俺も歌いながら、巨大ロボみたい!!って思う(笑)」
東郷「えーい、ドーン!!(笑)」
後藤「そうそう。このボタン押すと多分、ギターの喜多君が死ぬんだろうみたいなことになるから、そのボタンは押さないようにするみたいなね」
永井「あはははは(笑)すごい笑ってしまった」
社会の一員であるという意識を
どうすれば持つことができるのか?
永井「身体を一回通すって、ままならなさの経験でもあって。すごく時間がかかるわけですよね、イラレ使わないで文章を書くとか。めちゃくちゃ大変で、うわぁ、できない!みたいな」
東郷「時間かかりましたよ。気づいたら朝になってて(笑)」
永井「パンツを洗うとかもそうかもしれないし。なんじゃこりゃぁみたいな。でも、やってみる。それって、決してたったひとりで個人主義的に、自己責任的にやるってことではない。そこをいかに試みられるかっていうところなんだろうな、と」
東郷「ゴッチさんの巨大ロボ、アジカンチームがひとつの巨大ロボだとして、日本も一個の巨大ロボだし、地球全体でも一個の巨大ロボで。まあその、レイヤーというか、時限があって。だから僕はひとりでやってますとか、そこだけ切り取るとあれですけど、やっぱりそういう社会という巨大ロボなのか、大きい生き物なのか、の一部、臓器ほどデカくないけど…」
後藤「細胞?」
東郷「そう。細胞として振る舞う頭になってるときもありますね、やっぱりね。社会の細胞としてはこうしとこう、みたいな。ゴミは分別、みたいな」
永井「Dでは結論を出すというよりも、対話の最後はいつも問いをひらいて終わるんです。いまの話をうけて、自分がそういう細胞の一部だってふうに思える、つまりそれは社会の一員であるって思える意識って、どうやったら持てるんだろうっていう問いが生まれてきました。ずっとDとしても考えていることでもあるし、参加者のみなさんとも考えたい問いとしてひらいておきたいです」